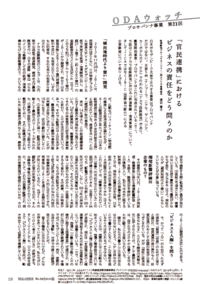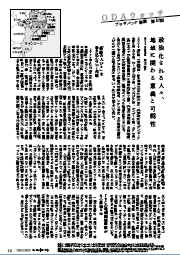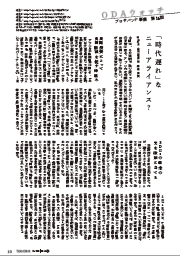ODAウォッチ:プロサバンナ事業の記事一覧
日本がモザンビーク北部で注力する事業はプロサバンナだけではない。北部5州(ナンプーラ、ニアサ、ザンベジア、カーボデルガド、テテ)で行われる「ナカラ回廊開発」があり、農業開発事業・プロサバンナはこれに包摂されている(注1)。
今回はこのナカラ回廊開発における「鉄道整備・港湾事業」について、そしてJICAではなくJBIC(国際協力銀行)による企業融資について取り上げる。
【No.329 400万人。人口の3分の1が今も恐怖と不安のなかで生きている (2018年1月20日発行) に掲載】
今回は、プロサバンナ事業の対象であるモザンビークの国家財政の状況と、それに関連しての日本政府の外交姿勢に関して取り上げる。ただでさえ遠いアフリカの、日本が関わっている援助事業とは言えその背景にある事柄、と捉えてしまえば、自身との関わりを見出すのは難しいかもしれない。
しかし、人々の暮らしが時の政治や経済に大きく左右されるのはどこの国でも変わりはない。私たちはそれを、どこまで意識できるだろうか。
【No.325 人権も多様性も否定される新しい時代でのJVCの立ち位置 (2017年4月20日発行) に掲載】
2009年以降、「官民連携・投資促進」の掛け声のもと、日本政府はモザンビーク北部5州(テテ州、カーボデルガド州、ザンベジア州、ナンプーラ州、ニアサ州)における「ナカラ経済回廊開発」に積極的に取り組み、日本の複数企業(三井物産、新日鉄住金など)が石炭開発や鉄道・港湾などインフラ整備に投資している。5州のうち3州はプロサバンナ事業の対象地だ。しかし現在、この地域は現地の人びとが「内戦」と呼ぶ状況にある。いったい何が起きているのか。
【No.324 「聖地」と呼ばれる街の「差別と暴力」に向き合う (2017年1月20日発行) に掲載】
今回は、この連載で取り扱っているプロサバンナ事業のような援助事業の背景にある、アフリカを対象とした新しい国際的な投資/開発政策の枠組みに関して取り上げたい。援助の現場で起きていることには、それが生み出される背景が必ずあり、私たちはそれを知る必要があるだろう。
【No.323 イラク戦争は共存の社会を壊し憎悪を生み続けている (2016年10月20日発行) に掲載】
モザンビークは日本からは距離的には遠い土地だ。しかしそこには、日本のODAによるプロサバンナ事業に対して抵抗運動を続ける数多くの農民たちがいる。農民らしく地に足をつけ、かつ目指す遠くの目標を見据えて、土地と暮らしと未来を守るための闘いを今も続けている。
【No.321「紛争経済」が支える避難民の生活を変えるために目指すこと (2016年7月20日発行) に掲載】
これまでプロサバンナ事業に関して外務省やJICAと議論してきて、すでに3年以上が経つ。この間、ずっと考えてきた言葉がある。「農民主権」である。政府と私たちのこれまでの議論は、この言葉の解釈をめぐって行われてきたと言っても過言ではない。
【No.321「紛争経済」が支える避難民の生活を変えるために目指すこと (2016年7月20日発行) に掲載】
プロサバンナ事業の行方はいまだ予断を許さない。今号でご報告する事態を受け、日本のNGOは、事業の現状と問題点を取りまとめた抗議および事業の抜本的見直しを求める要請書、ならびに公開質問状を外務省・JICAに提出した(注1)。ぜひ記事と合わせてお読みいただき、日本の援助の実態をウォッチし続けていただきたい。
【No.320 HIV/エイズのスティグマからの解放 (2016年4月20日発行) に掲載】
この連載ではこれまで、プロサバンナ事業をミクロな視点、すなわちその実施の現場において何が行われているかを中心に批判してきた。住民や農民にとって、それがどういう意味を持つかが援助の基本だからである。今回は、逆にマクロな視点からプロサバンナを鳥瞰して、その全体像から見えてくる問題点を指摘してみたい。
日本国益のための援助
これまでアジア一辺倒だった日本のODAも、TICADなどに見られるように今では「アフリカ開発」をODAの柱のひとつに位置付けている。外務省がモザンビーク国をどのように認識し、その中でJICAはプロサバンナを含めてどのような開発を目指しているのかを、彼らが発した政策文書や発言をもとに探ってみる。
ODAの政策文書のひとつに国別援助方針がある。そこでは、「同国は、...資源が豊富であり、...農業開発の余地も大きく、...人口の大多数が農業に従事しているが、その大部分は生産性の低い零細な生産活動にとどまり、...企業活動は未発達である」とされており、「回廊と周辺地域を結ぶ道路・橋梁改修やナカラ港の整備・電力等のインフラ整備を支援するとともに、...(プロサバンナ事業)により、農業開発支援に積極的に取り組み、包括的な回廊開発支援を行う」とある。
要するに、外務省は古典的な近代化の視点から同国を「途上国」と認識しており、生産性を高め、インフラ整備し、輸出振興して国の経済を大きくするためには企業活動の発達が不可欠、という考え方だ。プロサバンナもここに位置付けられている。そして、その包括的な青写真が「ナカラ回廊開発計画マスタープラン」である。筆者が委員をしている「開発協力適正会議」で同地域の電力配電網計画を検討した時、外務省幹部から次のような発言があった。
「日本企業のビジネス環境整備のためのインフラ整備という観点から、日本企業の関心が高い地域・分野を対象に、案件の形成を目的に戦略的マスタープランの策定を進めている。」(第19回2014年12月16日)
この会議は、国益論者の委員が多いこともあって、それに誘引されて外務省もJICAも本音を語ることが多い。他国に負けずに日本企業にいかに受注させるか。ODAの評価も、そこを中心に論じられる。別の会合でも、外務省はインドにおける高速鉄道(新幹線)事業獲得競争で中国に勝ったことに熱弁をふるっていた。
【No.319 TPPは日本と海外の市民をどこに導くのか (2016年1月20日発行) に掲載】
7月にモザンビーク最大の小農組織UNACのメンバーが来日し、8月は3週間強に渡る現地調査を実施した。9月にはモザンビークより元農業副大臣・現プロサバンナ担当一行が来日し、意見交換の場を持つなどしたが、今回は調査中の出 来事から「事業の成果」について考えてみたい。
「役に立つ」支援への不満?
乾期だというのに、目の前に広がる緑あふれる見事な畑。モザンビークで訪ねた農民組織の共同畑だ。5ヘクタールの畑の真ん中に貯水池があり、水路が畑中に張り巡らされている。数年前に農民らが手で掘ったという。土曜日の朝 早くなのに、すでに男女合わせて10人を超えるメンバーが熱心に作業をし、小さな子どもたちも遊びながら手伝っている。
昨年この農民組織にプロサバンナ事業より電動水ポンプが貸与され、種が提供された。今年4月の調査で、この組織のリーダーに話を聞いた際、事前の合意にもかかわらず、自分たちが希望していたものとは違う種が遅れて配られ、満足いく生産ができず、水ポンプ代が返せない可能性があるとの不満と不安を話していた。
今回はその後の話を聞いた。今年の種は、担当官と交渉し、自分たちが店で購入したために問題はなかったという。また、電動水ポンプには、一定の速度で早く水を畑に廻せる利点がある(「それで生産性があがったか?」との問いに回答はなかったが)。要は「それなりに役に立っている」とのことだった。だが、農民らが強調したのは、次の一言だった。「プロサバンナは私たちの話をまったく聞かない」
【No.318 アジアにおける外部環境の変化のなかでJVCは何ができるか (2015年10月20日発行) に掲載】
プロサバンナ事業に対し、これまでその事業内容の改善だけではなく、事業策定プロセスへの小農の「意味ある参加と対話」を求めて活動してきたが、3月末、プロサバンナ事業の青写真となる「マスタープラン」の「ドラフト・ゼロ」なるものが突如として公表された。そして翌4月に、この200ページ以上におよぶ文書に対して「小農たちの声を聞く」ために、小農や市民社会が準備時間を取れないほど直前の連絡の後、「公聴会」が実施された。私も急遽現地に飛んで参加したが、そこに小農たちの意味ある参加はなかった。※注①
日本の畑を歩くモザンビークの研究者
6月半ば、プロサバンナ事業の「マスタープラン・ドラフト・ゼロ」に関する公聴会の「やり直し」を求める声明を現地NGOらとともに出した、モザンビークの「農村モニタリング研究所(OMR)」のジョアオン・モスカ教授が緊急来日した。モスカ先生は、同国の農業・農村開発の研究に40年間携わっている。一週間弱の滞在期間に、研究会や議員訪問、NGOとの会合などが詰め込まれているなか、千葉県成田市三里塚を2時間だけ訪問することができた。この短い訪問を、「わんぱっく野菜」を運営される有機農家の石井恒司さんが、ご多忙ななか、快く受け入れてくださった。
【No.316 軍事優先の思想への対置として国境を超えた市民協力を (2015年7月20日発行) に掲載】