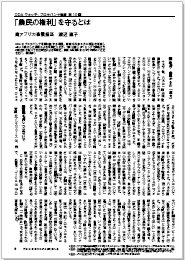ODAウォッチ:プロサバンナ事業の記事一覧
ODA のプロサバンナ事業に関する連載。前回は今年8月に現地を訪問しJICA と同行した高橋による報告だったが、今回は同じタイミングで農民たちの話を聞き取ってきた渡辺による報告だ。前回の報告と合わせてお読みいただきたい。(編集部)
政府・企業からの「圧力」
十月下旬、八月に一緒に現地調査を行なったプロサバンナ事業対象ナンプーラ州の農民組織UPC-Nの代表と首都マプトのNGO、ADEORUスタッフから連絡を受けた。ADEORUが調査で得た情報に基づきプロサバンナ事業の実態についてのプレスリリースを発表したところ、事業と契約している現地企業が「書かれた内容は間違い」だから「先のプレスリリースが間違いだったとする新たなリリースを出すよう」伝えてきたという。UPC-Nには政府関係者が訪問し、プレスリリースの内容の事実確認と「話を聞いた農民の写真を渡すよう」言われたそうだ。このことは企業や政府からの「圧力」として現地では受け止められている。
八月の調査では、農民たちを訪問した際、その多くで話の前にまず畑を一時間以上歩いて見せてもらい、その後一時間以上かけてゆっくり話を聞いた。彼らが連れていってくれたのはプロサバンナ事業下にある畑ではなく、これまで地道につくってきた畑だ。農民同士が語らうような場となったことで(ADEORUスタッフも農家の出身)、さまざまな本音がポロポロと出てきた。その結果、プロサバンナ事業が地域の人々の実情を包括的に捉えておらず、すでに実地で進められている「モデル普及」事業※注①がモデルとしてまったく機能していないことなど、事業の様々な課題が明らかになった。
今回の訪問先のひとつには、「モデル普及」事業における契約企業で、近隣の農民と契約栽培を行なっているMatharia Emprendimento 社( 以下ME社)がある。訪問の最中に、このME社が「農民を追い出し、土地を奪った」という話を聞き、実際に土地を追われたという農民たちに急遽話を聞くことにした。また、同企業と契約栽培をしている農民組織のメンバーや企業に雇用されている労働者にも会った。そこで語られたのは、不公正な契約栽培、モザンビークの最低労働賃金(月約一万円)を下回る形(月約三千円)での雇用状況、そして土地を追われ、新たな地で「生産する気を失った」という農民たちの声だった。
【No.313 今も続く紛争、その中で何を目指すのか (2014年12月20日発行) に掲載】
今回は再びプロサバンナ事業をとりあげる。7 月にモザンビークで開催された国際会議に参加した渡辺が、そこでの議論を通して感じた「音のない戦争」。それを止めるためにはどうすればいいのだろうか。(編集部)
分野を超えた反対へ
六月二日、モザンビークにおいて「No! to ProSAVANA」という全国キャンペーンの開始が発表された。キャンペーンにはナカラ回廊地域の小農および小農組織連合であるUNAC、女性フォーラム、人権リーグ、環境団体など分野を超えた八つの全国組織が参加している。
プロサバンナについて語る際、よく聞かれる質問がある。「日本企業やプロサバンナ事業は土地収奪を起こしているのか?」である。モザンビークでは本誌でも報告してきたとおり、海外投資企業による土地収奪はすでに頻発している。一方で、確かに日本企業による直接的な土地収奪はこれまでに報告されていない。であるならば、なぜ当地で全国キャンペーンが張られるほどの反対にあうのだろうか。
【No.311 市民に押し寄せる紛争や分断の波 (2014年8月20日発行) に掲載】
今回は、昨年に引き続き実施したモザンビークへの調査訪問の報告となる。詳細な調査結果は別途報告にまとめるとして、ここでは今回の訪問で高橋が見てきた風景から、そこに暮らす農民たちが開発から取り残される仕組みについて考察する。(編集部)
情報と権力の非対称性
今夏、モザンビークを再訪した。五名の日本の市民社会のメンバーで手分けをし、現地市民社会の協力を得てプロサバンナ事業の実態調査を行なった。今回の調査では、JICAにも協力・同行してもらうことで彼らの持つ情報を知ったり、彼らの農民への接し方を観察することができた。筆者も全日程でJICAが同行し、モザンビーク政府担当者との会合や事業地(農村)を訪問することができた。
今回の収穫は、事業を推進している現場コンサルタントの把握する情報が、これまでの意見交換会や公開文書から得た情報に比べ格段に多いという発見だ。当たり前と言えばそれまでだが、特に農業開発に関わる他ドナーや企業の動きが活発なことに驚いた。
【No.312 変わりゆく風景と暮らし (2014年10月20日発行) に掲載】
ODAのプロサバンナ事業に関する連載。7回目の今回は、前回で紹介したアグロ・フード・レジームの変化に関連して、その背景にある食と農をめぐる国際的な政治状況についてお伝えする。(編集部)
食と農を揺るがす変化
これまで、プロサバンナ事業が現地農民(特に小規模農家)に与える影響を中心に語ってきた。今回は、国際的なマクロな視点からプロサバンナ事業を考察してみたい。プロサバンナは、食と農のあり方を大きく変化させることに「棹差す」ために始められた事業である。これを「アグロ・フード・レジームの再編」と呼ぶ研究者もいる※注(1)。日本政府は、このレジーム・チェンジに積極的に関与することで、この分野でのリーダーシップを発揮し、その経済的メリットも享受したいと考えているのだ。ならば、私たちもその背景も知っておく必要がある。
【No.308 パレスチナの人びとの生きる力を支える (2014年4月20日発行) に掲載】
ODAのプロサバンナ事業に関する連載。6回目の今回は、事業そのものの問題というよりも、その背景にあって今の世界を取り巻く「アグロフードレジーム」について指摘する。(編集部)
「弱い個人」とは誰か?
「モザンビークは現在投資先として大きな注目を浴びており、この世界経済の流れは長い目で見て止めることができない。彼らの生活も変わらざるを得ない中、対応していけるようにすることが私たちに課せられた命題である」
これは、昨年十二月四~六日にかけて私がプロサバンナ事業地であるモザンビーク・ナンプーラ州と首都マプトを再訪、事業実施者側である日本大使館やJICAを訪問した際、彼らの発言に共通していた主張だ。これを聞いて私は驚いた。確かに時代の流れに沿って生活の変化に対応できるようにしていくことは必要だろう。だがそもそもその投資がモザンビークの人たちのためになっているかを問い直す必要はないのだろうか。
この一月、安倍総理はモザンビークを含むアフリカ三ヵ国を訪問、最終日に行なったスピーチのタイトルは『「一人、ひとり」を強くする日本のアフリカ外交』だった※注(1)。一方、これまで私がアフリカの人びとと活動をしてくる中で強く実感するようになったのが、いわゆる「貧困層」と呼ばれる人たちに出会ったとき、その状態は彼ら自身の能力や知識不足、弱さ等に起因するのではなく、いま私たちの周囲を取り巻き、当たり前のものだと思い込んでいる社会(構造)のほうに問題はないか、と疑ってみる必要があるということだ。実際、彼ら「一人、ひとり」は実に様々なことを知っていて、農業に限らず生活全般における能力に長けている。であるならばそんな彼らを「生きづらくさせている何か」があるのではないかと思ったのである。
【No.307 JVCはアジアで今後何をすべきか (2014年2月20日発行) に掲載】
ODAのプロサバンナ事業に関する連載。5回目の今回は、ODAの事業プロセスにおいて住民対話を保障する仕組みについて指摘する。NGO 側は、以前からこの仕組みをプロサバンナ事業に対して適用することを求めてきたのだが、それはまだ実現していない。(編集部)
事業を中断しない理由は
プロサバンナ事業について外務省と意見交換会を続けて、すでに一年が経った。この間、事業の目的が「小農支援であることを確認できたことは前進だ。しかし、それに伴って様々な問題も浮き彫りになった。曖昧だった目的が明確になったことで、隠されていたものが可視化され、「言っていること」と「やっていること」のギャップが明らかになったのだ。そのひとつが、対話のあり方だ。特に援助事業の場合、対話は事業の目的(援助を受ける者のニーズ)と内容(援助する者の活動)を整合させる上で必要なものだ。その不備を修正するには事業の中断が当然だと思う。
しかし、優秀な「官僚」の発想は違う。事業を走らせながら対話のあり方を改善する、というのだ。まるで、加速する列車を走らせたまま、線路脇にたたずむ人々の声を「丁寧」に聞いていくアクロバティックなことができると言う。あるJICA幹部は「中断したら再始動できない」と宣っていた。運転席には座っているが、どうもアクセルの踏み方しか知らないようなのだ。暴走列車あるいは冷却コントロールが効かなくなった原発と同じだ。奇妙な自信を持つ相手に「暴走」を止めてもらうにはどうするか?『白熱教室』で有名になったサンデル教授の引用を思い出す。「大勢を救うための一人の犠牲は正当化できるか。」「暴走列車」に乗せられた多数の農民を救うために、列車に身を投げる犠牲者が必要なのだろうか。
【No.306 「人道支援」の最前線にあって考える (2013年12月20日発行) に掲載】
ODAのプロサバンナ事業に関する連載。4回目の今回は、8月6~18日にモザンビークの事業対象地を中心とした訪問調査に赴いた2名のスタッフによる報告が中心だ。この調査は、「モザンビーク開発を考える市民の会」を始めとする複数の日本の団体によって共同で実施されたもの。帰国後に事業の中断と見直しをもとめる声明を発表(9月30日)、調査の詳細な報告書も10月末公開を目指して作成中である。(編集部)
遠い国での日本の事業
バンコクとヨハネスブルグでの乗換時間を含めて、モザンビークの首都マプトまで約二十六時間。国内線に乗り換えて北部の州都ナンプーラまで二時間。ナンプーラから舗装されていないダートを四駆で三時間ほど内陸部に向けて揺られ、ようやくナンプーラ州西部、リバウエ郡イアパラに着く。ここは、プロサバンナ事業のリークされたマスタープラン案※注(1)でクイック・インパクト・プロジェクト※注(2)の対象地として指定された所であり、特に土地の事前確保が計画されている。私は、三つに分かれた今回の調査チームの一つとして、この地域を訪れ、農民から話を聞いた。知りたいことは三つあった。土地収奪の実状、そして本事業に対する農民の理解度、最後に農民たちの暮らしである。いずれも「小農支援」を考える上で不可欠な項目だが、マスタープラン案には書かれていない。
【No.305 JVC国際協力コンサート (2013年10月20日発行) に掲載】
ODA のプロサバンナ事業に関する連載。4 回目の今回は、8月6~18日にモザンビークの事業対象地を中心とした訪問調査に赴いた2名のスタッフによる報告が中心だ。この調査は、「モザンビーク開発を考える市民の会」を始めとする複数の日本の団体によって共同で実施されたもの。帰国後に事業の中断と見直しをもとめる声明を発表(9月30 日)、調査の詳細な報告書も10 月末公開を目指して作成中である。(編集部)
訪問調査を実施
訪問調査に参加するという形で、私は今回初めてモザンビークを訪問した。プロサバンナ事業( 以下本事業) についての経緯を知り、これまで外務省・JICAとの協議にも多少なりとも関わってきたなかで、いったい現地では実際に何が起きているのか、外務省・JICAによる本事業の説明や約束は本当に実施されているのか、直接見聞きして確かめたかったからだ。
結論から言えば、「説明・約束」と「現実」の間には大きな齟そご齬があったと言わざるを得ない。以下、外務省・JICA側が示してきた「『小農は土地を有効活用して生産できておらず貧しい(1) 』ために本事業は『投資によってモザンビークの小農を豊かにする(2)』ことを目的としており、事業内容については『時間をかけて対話していきたい(3)』」という三つのポイントにしぼって報告する。
【No.305 JVC国際協力コンサート (2013年10月20日発行) に掲載】
ODA のプロサバンナ事業に関する連載。3 回目の今回は、6 月のTICAD の際に提出された公開書簡の内容と、「食料安全保障」と「食料主権」というふたつの言葉の違いからこの事業の問題点を考える。(編集部)
国際会議の陰で
アフリカ五十四ヵ国のうち五十一ヵ国が参加した第五回アフリカ開発会議(以下TICAD)は六月三日、『横浜宣言』※注(1)を作成して閉幕した。最貧国が集まるアフリカを底上げするために一九九三年に日本主導で始まったTICADだが、今回は「躍動するアフリカと手を携えて」を基本テーマとし、民間セクター主導による経済成長を重要視し、その恩恵をあまなく行きわたらせることを目指す方向性が強く打ち出されたものとなった。特に、インフラ、製造業、観光業に加え、農業への投資促進が強調し、自給自足の小規模農業から商業的農業経営への移行を目指すとしている。
この大きな会議に、私たちの招きで二度目の来日を果たしたモザンビークの農民たちは、ホスト国の安倍首相にレセプションで会い、民間投資による大規模農業開発に明確に反対する意を伝える公開書簡※注(2)を手渡した。この書簡のなかで、農民たちは次の様に訴えた。
【No.304 国境が引かれ、対立と不信が残された後で (2013年8月20日発行) に掲載】
前号から連続してとりあげているODAのプロサバンナ事業。2回目の今回は、「農民主権」という視点からこの事業の問題点を見てみたい。(編集部)
モザンビークから招へい
去る二月二十四日~三月一日、日本・ブラジル・モザンビーク三角協力によるモザンビーク北部地域における大規模農業開発事業「プロサバンナ」に関連して、日本の市民社会の招聘で、UNAC(モザンビーク全国農民組織)の二名と同国の環境団体JA(Justica Ambiental) の一名が来日した。外務省やJICAとの面会や一般向けセミナーを通じて、彼らが語ったことをお伝えする。
現在、モザンビークでは人口の七割が農村部に暮らして自給的農業を営み、国内総生産の三割を生み出している。プロサバンナ事業の対象地域においても、家族的経営農業のもと主食のメイズや豆、葉物野菜や根菜類など様々な作物が収穫されている。「サバンナ地域」というイメージに反して雨も降ることから森林も豊富で、人びとは森林からも木の実や果実、動物などの多くの食料を得ている。
プロサバンナ事業は、こうした地域において千四百万ヘクタールという莫大な土地を開発し、輸出用大豆の栽培を目的とするものだ。当然のように小農の土地は収用され、森林も伐採前号から連続してとりあげているODAのプロサバンナ事業。2回目の今回は、「農民主権」という視点からこの事業の問題点を見てみたい。(編集部)ODAウォッチ:プロサバンナ事業 第2回されるだろう。事業を推進する側の外務省・JICAも、すでに対象地域の住民移転の可能性を認めている。そして現地の農民たちはこの事業に関する適切な情報にアクセスもできず推進プロセスに参加もできないことから、大きな不安を抱えている。
【No.301 生き残った私たち3 (2013年4月20日発行) に掲載】