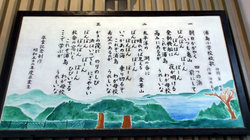気仙沼支援活動レポート
浦島地区振興会(以下、振興会)の活動がスタートし、JVCは、組織構成や今後の活動について、役員会や委員会の場で住民の方々と協議を行ってきました。
振興会の体制に関して、振興会は、(1)施設利用部、(2)地域資源開発部、(3)環境・文化部という三つの部会で構成されることになりました。(1)では、昨年度をもって閉校した浦島小学校の施設の活用法と維持管理方法の検討を行います。今後、勉強会や先行事例の視察を通じて、地区住民の意向に合致した活用法を要望書として取りまとめ、市へ提出することを目指します。(2)では、「海・山・里・人」といった浦島地区の地域資源の発掘、それらを生かした体験ツアーなどの検討、(3)では、防災・減災対策や郷土芸能に関する活動を行う他、地区住民の親睦を図るための運動会や盆踊りなどの地区行事の開催を模索します。
6月2日、防災集団移転のアドバイザー派遣を実施し、地区ごとの相談会を開催しました。今回の相談会では、主に家づくりに関する協議が行われました。
相談会ではまず、家づくりの上で想定される四つの住宅建設方式について、アドバイザーから説明がなされました。一つ目の方式は、(1)「共同発注方式(ハウスメーカー)」で、複数の住民がまとまってハウスメーカーに発注を行います。住民は、ハウスメーカーが用意する商品化住宅のラインナップから住宅を選択することになります。二つ目は(2)「共同発注方式(工務店)」で、こちらも複数の住民がまとまって工務店に発注を行います。この場合、工務店は商品化住宅をもたないため、住宅の設計は住民の希望に応じて行われます。三つ目は(3)「共同建設方式」で、基礎工事や塗装工事などの各種専門工事を担う業者に対し、住民が組織を作りそれぞれの業者と契約を結び、共同で住宅を建設していきます。四つ目は(4)「個別建設方式」で、住民が個別に設計者・施工者を選定し、住宅を建設します。
4月28日(日)、10回目となる防災集団移転のアドバイザー派遣を実施し、梶ヶ浦・小々汐・大浦の地区ごとに協議会を開催しました。各地区で事の進め方や進み具合に多少の差はありますが、造成地の詳細設計などがほぼ固まるにしたがい、個々の家づくりと同時に全体としてのまちづくりについても話し合われるようになってきました。
梶ヶ浦地区では、前回の協議会で全世帯の区画割が決定したことを受け、家を建てる際に皆が守るべき最低限の取り決めについての話し合いが始まりました。「お隣の建物とはどれぐらいの間隔をあければいいだろうか・・・」「窓の位置は・・・」このような疑問に対し、アドバイザーから建築基準法や民法上の説明や経験に基づくアドバイスなどがなされました。また、家を建てるということがあまりに漠然としているため、建てたい家のイメージづくりに役立つアンケートシートが紹介され、今後の段取りやスケジュールなどについてもわかりやすく説明されました。次回以降は、住宅地の見学や家にまつわる様々なテーマを設けたワークショップを行っていくことになりました。
「浦島地区(※)のこれからのあり方を考えていく必要があるのではないか」
JVCが活動する鹿折地区四ヶ浜において、新たなまちづくりを考える「浦島地区振興会」が立ち上がりました。
震災以前から少子高齢化の影響に悩まされてきた浦島地区では、震災により、地域住民が離散したことで、旧浦島小学校の閉校や集落の自治機能の低下など、様々な問題が表面化しました。加えて、大島架橋事業や三陸自動車道の整備などの大型公共事業が計画されている同地区では、これらの事業により、交通面での利便性が向上し、訪問者の増加が見込まれる一方で、自然環境などの地域資源が影響を受ける可能性があります。
このような状況の下、地域の豊かな自然環境や風土を守りつつ、住みやすく活気のあるまちづくりを行っていくことが当振興会の主たる目的です。
JVCが活動する鹿折地区・四ヶ浜(しかはま)では、牡蠣、帆立貝、ワカメ、コンブの養殖が盛んに行われています。この度、ワカメの収穫時期となる2月~4月にかけて、地元の養殖業者の協力を得て、養殖体験を3度実施しました。体験を通じて生産者と消費者を結びつけることで、地域の養殖業の活性化を図るとともに、養殖業への理解者を増やすことがその目的です。
3月31日、2012年度最後となる防災集団移転のアドバイザー派遣を実施し、地区ごとの住宅相談会を開催しました。この間検討を重ねてきた造成地の詳細設計がほぼ固まったため、今回の相談会では、住宅を建設する区画を決めるための抽選会を行いました。
大浦(おおうら)の相談会では、最初に災害公営住宅整備事業の進捗が共有されました。大浦地区では、10戸の災害公営住宅が集団移転の造成地に併設される予定となっています。この災害公営住宅の整備内容についての説明が協議会からなされました。続いて開催された抽選会では、予備抽選、本抽選を経て、区画を選ぶ優先順が決定されました。そして次回の相談会において、この順番に従い各住民の区画を定めていくことが確認されました。
気仙沼市立浦島小学校は、惜しまれながら63年の歴史に幕を閉じました。同小学校は、昭和25年の独立開校以来、四ヶ浜唯一の教育機関として1200名以上の卒業生を世に送り出してきましたが、近年の少子化や震災の影響により、児童数が大幅に減少し、平成24年度をもって閉校されることとなりました。
JVCは、これまで学校行事への開催協力や国際理解授業、畑作りなど、様々な形で地域住民にとっての拠り所である浦島小学校を支援してきました。今回の閉校記念事業に当たっても校歌のCD製作や閉校式典の準備、閉校式当日の運営などに協力してきました。
「ぽんぽん ぽーん ぽんぽん ぽーん 発動機船に夜が明ける ♪ 」
四ヶ浜の住民が少年少女時代に学んだ浦島小学校の校歌の一節である。震災の影響で児童数が7名にまで減少した本校は、この春に5名の最後の卒業生を送り出した後に閉校を迎える。
2月3日、防災集団移転に関わるアドバイザーが気仙沼を訪れ、地区ごとの住宅相談会を開催しました。前回のレポートでお伝えしたように、現在、大浦(おおうら)・小々汐(こごしお)・梶ヶ浦(かじがうら)の防災集団移転促進事業では、造成地の詳細設計が進められています。そのため相談会の中では、詳細設計をもとにしたテーマに沿って話し合いが行われました。
まず小々汐の相談会では、造成地内に整備される擁壁(ようへき)の検討が行われました。協議の結果、宅地と宅地の間、宅地と道路の間に設けられる擁壁の種類や長さの要望が、設計に関わるコンサルタント会社に伝えられました。また、住民自身で設置する宅地内の側溝については、誰がどの場所に設けるかについて、住民間での申し合わせが定められました。
1月20日の昼下がり、東京都江戸川区で開かれた「江戸川太鼓20周年記念の会」で、気仙沼市・小々汐の太鼓団体からのメッセージが披露された。
2011年の初秋、JVCは、大震災の津波により存続が危ぶまれていた「小々汐打囃子保存会」への支援を決め、各方面に太鼓などの寄付を呼び掛けた。その際、真っ先に協力を申し出てくれた「江戸川区太鼓連盟」の中核を成す団体が、このたび20年という節目の年を迎えたのだ。