その他・未分類の記事一覧
日本や欧米の主要メディアではイラク関連の報道の影に隠れていますが、今月12日、西岸地区全土にイスラエル軍が大規模な地上侵攻を開始し、ガザ地区でもここ数日間イスラエル軍による空爆が毎晩繰り返されています※注(1)。ガザ地区からは、小型ロケットがイスラエルに向かって発射されています。
歳を取ると時が過ぎるのが早くなる...という誰もが言いそうなセリフが自分にも実感できる日々です。先日3月15日~4月15日まで年度末事業業務と報告のために一時帰国しましたが、再び現地に戻ってきて既に一月近く経ってしまいました。今日は遅ればせながら帰国中にお世話になった方々への御礼とご報告をしたいと思います。
今回は2013年度ガザ事業のメインドナーである国際ボランティア貯金の年度末報告書の作成のために帰国しましたが、その傍らで、同じくガザ事業を支えて下さっている多くの団体、個人の方々へのご挨拶と、ガザの事をより多くの方に知っていただくことを目的に、6回の講演会・報告会を実施しました。3月21日-23日には数年ぶりに関西に出かけ、長年JVCパレスチナ事業をご支援いただいている日本聖公会・大阪教区の大阪聖ヨハネ教会をはじめ、パレスチナ支援を熱心に展開している、パレスチナの平和を考える会、大阪YWCA、また新しくパレスチナに興味を持って下さった南海ルーテル教会のご協力にて3回の講演会を開催させていただきました。合計100人以上の方にご来場いただき、ネット上の動画公開サービスUstreamでは講演会の公開もしていただきました。現地赴任中は日本にいるパレスチナ関係者とお話しする事がなかなか難しいですが、今回は長年パレスチナ問題に関わっている方々と熱心な議論、情報交換を行う事が出来て、私自身多くのインプットがありました。不勉強な自分を反省しつつも、関西で活発に動いているパレスチナ支援ネットワークへの関わりを再構築する機会となり、大変有意義な訪問になりました。
皆さん、こんにちは。
東京担当の並木が11月11日に現地便りに掲載した、ムハンマド・アッサーフについての記事にコメントしたところ、「せっかくですから今野さんもこのネタで書きましょうよー!笑」と返ってきたので、アラブ・アイドルをリアルタイムで見ていた隠れアッサーフ・ファンとして、何か書かざるをえなくなったエルサレム事務所の今野です。
さて、「ロケット」というニックネームを持つムハンマド・アッサーフには、多くの逸話があります。その1つに、次のようなものがあります。
彼は、アラブ・アイドルの最初のオーディションを受けに行った時、ガザ地区からなかなか出られず、当日エジプトの会場に着いた時にはすでに登録が終わっていました。ところが、アッサーフは壁を乗り越えて会場に侵入し、オーディションを受ける人たちの待合室で歌ったそうです。それを聞いたエジプト国籍のパレスチナ人男性が、「こいつは天才だ。俺が受けても受からないかもしれないけど、こいつだったら優勝するかもしれないぞ・・・」ということで、アッサーフに自分の登録番号を渡したそうです。だから、アッサーフが最初に歌った映像では、彼はエジプトのゼッケンをつけているというわけです。
大阪の市民団体、パレスチナの平和を考える会の会報誌「ミフターフ」35号(2013年4月刊行)に、今野エルサレム事務所現地代表のインタビューが掲載されました。このインタビューでは、パレスチナの現状や国家承認問題などについて、現場の活動を通して見てきたことを率直に述べています。
4.国際援助にかんして
(1)まず、日本のODAに関してですが、昨年、外務省は、「対パレスチナ自治区国別援助方針」を公表しました。JVCは、事前に外務省との意見交換もされていたわけですが、援助方針の内容について、実際のODAの現状も踏まえ、率直な感想をお聞かせください。
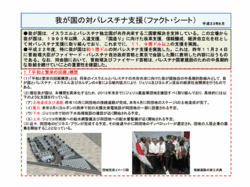 日本政府による対パレスチナ支援のファクトシート。外務省ウェブサイトより
日本政府による対パレスチナ支援のファクトシート。外務省ウェブサイトより援助方針については、私の個人的な意見だけ申し上げます。まず、評価できる点は3つあります。第1に、今回の援助方針には「占領」の問題について明確に述べられており、占領下における具体的な問題にも触れていることは、高く評価できます。しかしこれは、国際法や国連決議に照らし合わせれば当然とも言えます。2つ目の評価できる点は、パレスチナの経済的・社会的自立がイスラエルとの平和共存のために必要不可欠であるとの認識が示されていることです。第3に、「パレスチナ自治区」の中にC地区と東エルサレムがきちんと含まれており、そこでの支援を進めていく意思が示されていることも評価できます。C地区と東エルサレムは、イスラエル政府が事実上の自国への編入を進めているため、パレスチナ人の生活はとりわけ厳しく、支援も入りづらい現状があります。また、C地区と東エルサレムでの支援強化は、パレスチナ人の多くが求めていることでもありますので、この文言が今後具体化されていくのであれば、それ自体は素晴らしいことだと考えています。
大阪の市民団体、パレスチナの平和を考える会の会報誌「ミフターフ」35号(2013年4月刊行)に、今野エルサレム事務所現地代表のインタビューが掲載されました。このインタビューでは、パレスチナの現状や国家承認問題などについて、現場の活動を通して見てきたことを率直に述べています。
3.西岸地区とガザ地区双方にかかわること
(1)11月のガザ攻撃の際には、西岸地区におられたと思いますが、西岸の人々の様子はいかがでしたか?
私は、ガザ攻撃の際にはずっと東エルサレムにいました。なので、東エルサレムの状況しかお伝えすることはできません。
端的に言うと、エルサレムのパレスチナ人は、イスラエルの攻撃に強い怒りを感じる一方で、ガザからエルサレムまでロケットが届いたことにとても興奮し、喜んでいました。ロケットが着弾した翌日、東エルサレム市内の中学校に行ったのですが、生徒も先生もその話題で持ちきりでした。いつもやられっぱなしのパレスチナ人が、遠くエルサレムまでロケットを飛ばすことができたのだ、ということへの喜びや誇りの表れだったようです。私は正直その反応に最初は驚きましたが、彼らのそうした反応を異常と感じるのであれば、それは単に、パレスチナ人の閉塞感や怒りや憤りや無力感といったものを理解できていないだけなのだろうと思います。
大阪の市民団体、パレスチナの平和を考える会の会報誌「ミフターフ」35号(2013年4月刊行)に、今野エルサレム事務所現地代表のインタビューが掲載されました。このインタビューでは、パレスチナの現状や国家承認問題などについて、現場の活動を通して見てきたことを率直に述べています。
2.ガザ地区にかんして
(1)ガザ地区を訪ねられたのは、昨年が初めてということですが、特に印象的に思ったことがあれば、聞かせてください。
今回のインタビューを受けるにあたり、ガザ地区に初めて入った日の日記を読み返しました。そこに私は、次のように書いていました。
「ガザには、イスラエル側とガザ側で許可証を取得して、イスラエル領内から入った。ガザへは、エルサレムからガザ地区北部に設置されたエレツ検問所までタクシーで向かった。広大な農地の中に突如として分離壁が目に入ってきたが、手前の荒野と農地があまりに広大で、イスラエル領内からガザに向かって標高が下がり続けているため、分離壁は想像していたほどの存在感はなかった。
大阪の市民団体、パレスチナの平和を考える会の会報誌「ミフターフ」35号(2013年4月刊行)に、今野エルサレム事務所現地代表のインタビューが掲載されました。このインタビューでは、パレスチナの現状や国家承認問題などについて、現場の活動を通して見てきたことを率直に述べています。
1.西岸地区(東エルサレムを含む)にかんして
(1)昨年は、まず、パレスチナ自治政府の国連オブザーバー国家への格上げということがありましたが、そのことによって、具体的に何か変化した点はありますか?人々の生活や意識ということでもいいですし、JVCの仕事にかんしてということでも構いません。
JVCパレスチナ事業は現在、アドボカシー活動の他に、東エルサレムとガザ地区でパレスチナNGOと共に、保健医療の分野で活動をしています。その中で、国連オブザーバー国家への格上げというニュースがありましたが、結論から言うと、現地の状況は何一つ変わっていません。私が「アッ・スルタ(自治政府を指すアラビア語)」と言うと、パレスチナ人から「ダウラ(国家を指すアラビア語)です」と返ってくることはたまにありますが、本気で「○○だから国家と言えるのです」といった風に論じる人には会ったことがありません。
東京で下記のワークショップが開催されます。下記のワークショップだけでなく、1月11日から24日にかけて、日本各地で講演会・勉強会が開催されます(チラシ裏面を参照ください)。著名な学者と市民活動家を招へいした今回の一連のイベントは、「アラブの春」以降のパレスチナ/イスラエルでの和平の行方を知るとともに、パレスチナ/イスラエルと日本の市民社会が協働していく方法を考える良い機会にもなると思います。ぜひご参加くださいませ。
新年あけましておめでとうございます。さて、大阪で下記のイベントが開催されます。今後の和平の行方を知るとともに、イスラエルと日本の市民社会が協働していく方法を考える良い機会にもなると思いますので、ぜひご参加ください。
以下、イベント情報です。
2012年11日29日、国際連合総会にて、パレスチナが国連の「オブザーバー機構」から「オブザーバー国家」へと格上げされることが承認されました。賛成138カ国(フランス、イタリア、中国など)、反対9カ国(イスラエル、米国、カナダなど)、棄権41カ国(英国、ドイツなど)でした。日本政府は、今回の決議では賛成票を投じました。
ガザ地区でもガザ紛争の開始(現地時間11月8日)以降、これまで対立関係にあった2大党派のハマースとファタハが協調姿勢の方向に歩み寄っており、昨日(11月29日)もガザ市ではファタハなどの支持者が集まって国家承認への支持を表明するデモを開催していました。これまでガザ地区ではファタハの政治運動は厳しく制限されていましたが、昨日はファタハの支持者たちが満載のバスに乗ってうれしそうにファタハの旗を振りながらデモに向かっていました。
来日したこともあるパレスチナ人権センターのラジ・スラーニさんは昨日、今回のガザ紛争はイスラエルの政治・軍事・諜報面での失敗であると同時に、ガザ地区でのファタハ、ハマース、イスラーム聖戦運動など各党派の和解を進めるきっかけになったことから、紛争が始まった11月8日は「大きな歴史の転換点として記憶されるだろう」とおっしゃっていました。






