大阪の市民団体、パレスチナの平和を考える会の会報誌「ミフターフ」35号(2013年4月刊行)に、今野エルサレム事務所現地代表のインタビューが掲載されました。このインタビューでは、パレスチナの現状や国家承認問題などについて、現場の活動を通して見てきたことを率直に述べています。
4.国際援助にかんして
(1)まず、日本のODAに関してですが、昨年、外務省は、「対パレスチナ自治区国別援助方針」を公表しました。JVCは、事前に外務省との意見交換もされていたわけですが、援助方針の内容について、実際のODAの現状も踏まえ、率直な感想をお聞かせください。
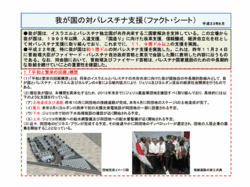 日本政府による対パレスチナ支援のファクトシート。外務省ウェブサイトより
日本政府による対パレスチナ支援のファクトシート。外務省ウェブサイトより援助方針については、私の個人的な意見だけ申し上げます。まず、評価できる点は3つあります。第1に、今回の援助方針には「占領」の問題について明確に述べられており、占領下における具体的な問題にも触れていることは、高く評価できます。しかしこれは、国際法や国連決議に照らし合わせれば当然とも言えます。2つ目の評価できる点は、パレスチナの経済的・社会的自立がイスラエルとの平和共存のために必要不可欠であるとの認識が示されていることです。第3に、「パレスチナ自治区」の中にC地区と東エルサレムがきちんと含まれており、そこでの支援を進めていく意思が示されていることも評価できます。C地区と東エルサレムは、イスラエル政府が事実上の自国への編入を進めているため、パレスチナ人の生活はとりわけ厳しく、支援も入りづらい現状があります。また、C地区と東エルサレムでの支援強化は、パレスチナ人の多くが求めていることでもありますので、この文言が今後具体化されていくのであれば、それ自体は素晴らしいことだと考えています。
しかし他方で、3つの問題が今回の援助方針にあると思います。1つ目は、ヨルダン渓谷での「平和と繁栄の回廊」構想に対する評価、2つ目は、「当事者間の信頼醸成」という条件付け、3つ目はODAが「現行和平プロセス」を進めるための手段として位置づけられているということです。この3つの問題について、順番にお話ししていきます。
まず、ヨルダン渓谷での支援について、援助方針には以下のように書かれています。
「パレスチナとイスラエル及びヨルダンとの地域協力を通じてヨルダン渓谷の経済開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想を提唱し、現在その中核的な事業としてジェリコ農産加工団地(JAIP)の建設に着手している。こうした我が国の「平和構築」に向けた地道な取組は、関係当事者からも高い評価を受けている。」
しかし、ここで触れられている「関係当事者」というのが、誰を指しているのか明瞭ではありません。例えば、これが、パレスチナ自治政府や開発事業に関わる一部の利害関係者だけを指しているのか、それともイスラエル政府やヨルダン政府も含まれているのか、さらには、より広くパレスチナの市民社会、特にヨルダン渓谷の住民も含まれているのか、全く知ることができません。援助の基本として、どのような方法でどの地域の誰を対象に調査をして、「高い評価」を受けたと結論付けているのかという点が重要なので、日本政府はこの点について明示すべきだと私は考えています。
また、ヨルダン渓谷でのイスラエルとの協力のもとで進められる開発については、日本国内のみならずパレスチナの現地においても、占領者たるイスラエルが利害関係者に含まれていることだけでなく、A・B地区に限定された開発であり、占領下での移動・輸送の制限を前提として計画が進められていることから、現在の占領状態・分離状態を恒久化するのではないかという危惧の声が上がっています。そのため、外務省やJICAが、占領地でのイスラエル政府を含んだ地域経済協力が占領の恒久化に結びつかないようにするために、どのような対策を講じているのかという点を、今後注視していきたいです。
2つ目の「当事者間の信頼醸成」に関する問題ですが、援助方針ではまず、日本政府が「中東和平の実現に貢献すべく(・・・)両当事者間の信頼醸成」に積極的に取り組んできたと述べられています。さらに、留意事項には以下のように書かれています。
「占領下という特異な状況下にあるため、ODA 事業の円滑な実施とその効果を最大限 確保するとの観点から、当事者間の信頼醸成も視野に起きつつ、イスラエル当局との各種調整・協力に然るべく配慮すると共に、関係当事国に対する必要な外交的働きかけも積極的に行う。」
これは、イスラエルとパレスチナの二国家解決のためには、両者の間での信頼醸成が必要だという意味で、それ自体、良いことのように聞こえるかもしれません。しかし、ヨーロッパから国家建設のために入植してきて一方的に住民を追い出し、さらに西岸とガザの占領を続けている側と、追い出された上に占領され続けている側の間での信頼醸成というのが、当事者であるパレスチナ人にとって何を意味するのか、日本の歴史も踏まえてよく考えておく必要があると思います。
援助方針の文言からは、信頼醸成の邪魔にならない限りは支援をするというスタンスがあるように読み取れます。それは、イスラエルがNoということは何もしないという意味なのでしょうか。もしそうであるならば、占領という構造的問題に対処することなしに援助だけでパレスチナ人の自立を達成できるのか、と問わざるをえません。現在の占領体制の最大の問題は、オスロ合意で凍結されてしまった冷戦終結直後の力の不均衡を、法的に維持してしまっている点にあります。この体制は、パレスチナ社会の経済的・社会的疲弊をもたらしている占領政策・分断政策と密接にリンクしています。したがって、こうした根本的問題に対処せずに、本当の「パレスチナ国家」が作れるとは思えません。それが可能と考えているのであれば、それはナイーブすぎるかと思います。しかし、たぶん日本政府で意図されているのはそこではないでしょう。
日本政府にとっては、どんな形であれ、イスラエル政府が嫌がらない形で「和平」が結ばれ、形だけでも「パレスチナ国家」ができて、それで外交上のポイントに加算され、結果的にそれが日本の資源安全保障に資すれば、それでいいんだと思います。しかも、「ODA事業の円滑な実施とその効果を最大限確保するとの観点から」という箇所からは、ODAが円滑に進むことが、日本政府やその関連下請け団体にとっての最大の関心事だということを示してしまっているように思います。こうしたスタンスには、正義とか法とか、そんなもので国際政治は動いていないという認識が反映されているのかもしれませんが、それは市民社会の一般的な価値観とは当然相容れないものです。もちろん、パレスチナ問題の根本原因が、シオニズムや難民問題や占領にあると思っている方も政府内にはいらっしゃると思いますが、そうした認識が援助方針から読み取れないというのは残念です。ですので、市民の皆さんが、日本が民主国家であると考えているのであれば、自分たちを「代表」している日本政府に対し、自らの価値観を実現する方向に動くように働きかけを行う必要があるでしょう。
第3に、援助方針には、以上述べた日本政府のスタンスと関係する、もう一つ根本的問題があります。それは、援助方針の中で、米国を始めとする「主要国」と協調し、「両当事者間の信頼醸成」によって問題解決に至ることができるという考えが示されているところにあります。こうした考えの背後には、問題の根源がイスラエルとパレスチナという2つのナショナリズムの対立にあるという、それ自体政治的な状況認識があるように思います。国際社会の当事者意識はどこへやら、全ての責任を「両当事者」に押し付けて、自分たちは喧嘩の見物人でいられると考えているように読み取れてしまうわけです。
イスラエル国家とパレスチナ人の間の国際政治における力の不均衡をもろに反映した交渉がうまくいかないことは、オスロ合意以降の経緯から明らかです。それがもたらした弊害もとても大きなものです。にもかかわらず、援助方針の文言からは、問題を2つのナショナリズムの対立構図に押し込めた上で、冷戦後の力関係を反映したオスロ合意の枠組内で、なんとしても解決をもたらそうという、政治的な意思を感じます。パレスチナ問題を考える上で、帝国主義の歴史や米国の対中東政策の経緯を踏まえ、本当に2つのナショナリズムの対立なのか問い直しておくことは必要不可欠です。それなしでは、今後、援助方針が状況変化に追い付けなくなり、根底から崩れることになるかもしれません。それを防ぐためにも、市民社会、特にNGOや研究者がオルタナティブを提示していくことが必要不可欠だと思います。
今回の援助方針では、関係各国への外交的働きかけとODAの両輪でパレスチナ支援を進めていこうという意思表示がなされており、それ自体は高く評価できますが、どのようなつながりを外交とODAの間に作っていくのかという点については明確ではありません。ですので、日本政府が今後、外交とODAの間にどのようなつながりを作っていくのかという点が、今後の支援の動きを見ていく上で重要なポイントになるだろうと思います。
(2)パレスチナ援助の「弊害」についての指摘はいろいろとありますが、そうした問題を乗り越えるパレスチナ社会の内発的な可能性について、現場で気づいたことなどあれば、お聞かせください。
こちらで働き始めてから、パレスチナ社会には内発的な可能性は潜在的にはいくらでもあり、単にそれを実現させるための外部条件が整っていないだけ、と感じるようになりました。
例えば、東エルサレム事業の医療チームの医師の給与は、平均的な給与相場よりずっと低く抑えられています。そのため、チームの2人の医師は、朝8時から午後2時までエルサレム事業で働いた後、東エルサレムにあるイスラエルの保険会社が運営する医療クリニックで夜遅くまで働いています。彼らがメールを見るのは帰宅後なので、時には夜10時とかにその日の活動の写真を送ってきてくれます。イスラエルの医療クリニックの方が給与は高いし、将来も安定するかもしれません。それでも彼らがパートナー団体の「医療救援協会」(MRS)で働き続けているのは、パレスチナ社会に貢献したいという強い気持ちと、活動の現場で一般の人たちから受ける大きな尊敬と感謝からだと思います。ガザの人々も同様で、外部から何度叩かれても、自分たちの未来と能力を信じて、本当に身を粉にして働いています。
私は、パレスチナ社会の中で働き始める前は、「占領の構造はなんてひどいんだ。こんな構造的暴力の中ではパレスチナ社会に未来はないんではないだろうか」と悲観的になっていました。しかし、実際に事業に携わるようになって、現場で日々一生懸命働いているパレスチナ人と一緒に動きまわるようになって、「どんなに占領がひどくても、きっと彼らがこの社会を支えていく。どんなことがあっても彼らはくじけないし、ジョークを飛ばしながら柔軟に対応していく。だから、パレスチナの未来はきっと大丈夫だろう」と楽観的に物事を見るようになりました。
もちろん、占領と分離、そしてイスラエルへのパレスチナの経済的な従属関係は、パレスチナ社会に様々な問題をもたらし、少しずつ社会をむしばんでいます。それに対する根本的な解決が必要です。しかし他方で、草の根で日々の問題を解決し、一歩でもいいから前に進もうと奮闘している人々がたくさんいるということを、私たちは忘れてはいけないと思います。それを忘れた所から出てくる「解決」は、上からの押しつけであって、決して現地の人々を幸せにする解決にはならないだろうと思います。
(了)
この活動への寄付を受け付けています!
今、日本全国で約2,000人の方がマンスリー募金でご協力くださっています。月500円からの支援に、ぜひご参加ください。
郵便局に備え付けの振込用紙をご利用ください。
口座番号: 00190-9-27495
加入者名: JVC東京事務所
※振込用紙の通信欄に、支援したい活動名や国名をお書きください(「カンボジアの支援」など)。
※手数料のご負担をお願いしております。
JVCは認定NPO法人です。ご寄付により控除を受けられます(1万円の募金で3,200円が還付されます)。所得税控除に加え、東京・神奈川の方は住民税の控除も。詳しくはこちらをご覧ください。
遺産/遺贈寄付も受け付けています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

