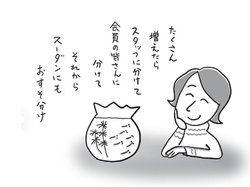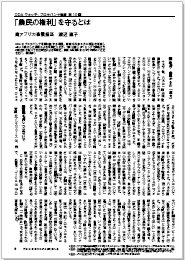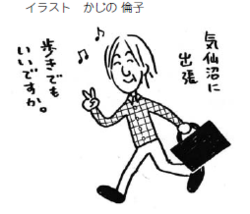Trial&Error掲載記事
今年の夏からメダカを飼っています。近所のお蕎麦屋さんの店先から、我が家にやって来ました。最初は6匹でしたが、3匹に減り、そして今は7匹がベランダの小さなメダカ鉢で元気に泳いでいます。
メダカをいただいたお蕎麦屋さんは、家族経営でとてもアットホームなお店で、10年近く通っています。今は2代目がお蕎麦を打っていますが、お父さんの時代は、お寿司屋さんだったそうです。子どもの歳が近いこともあり、家族ぐるみのお付き合いで、ときどき「これ持っていって」とお惣菜などを分けてくれます。ある日、お母さんが、「メダカ、持ってく?」と空き瓶にメダカを入れて、持たせてくれました。蓋の閉まった瓶の中で、メダカが窒息するのではないかと心配で、急いで家に持ち帰りました。そしてその週末、近所の金魚屋さんでメダカ鉢や水草を調達し、正式に我が家の「住魚」になりました。
それ以来、ベランダの鉢に顔を近づけてはメダカを眺めるのが毎日の日課となりました。あるとき、体調3ミリほどのメダカの赤ちゃん数匹を見つけたときは、感動しました。あまりの小ささに見つけるのも一苦労で、ある日見つけられずに「食べられちゃったかな」と思っていると、翌日にひょっこり現れて「おお、生きてたか!」と一喜一憂です。3歳になる息子は、「毎日ママは長いことメダカ鉢をのぞいて何をしてるんだろう...」と思っているはず。このメダカたち、たくさん増えたら、癒やしのおすそ分けをしたいと思います。
【No.319 TPPは日本と海外の市民をどこに導くのか (2016年1月20日発行) に掲載】
この連載ではこれまで、プロサバンナ事業をミクロな視点、すなわちその実施の現場において何が行われているかを中心に批判してきた。住民や農民にとって、それがどういう意味を持つかが援助の基本だからである。今回は、逆にマクロな視点からプロサバンナを鳥瞰して、その全体像から見えてくる問題点を指摘してみたい。
日本国益のための援助
これまでアジア一辺倒だった日本のODAも、TICADなどに見られるように今では「アフリカ開発」をODAの柱のひとつに位置付けている。外務省がモザンビーク国をどのように認識し、その中でJICAはプロサバンナを含めてどのような開発を目指しているのかを、彼らが発した政策文書や発言をもとに探ってみる。
ODAの政策文書のひとつに国別援助方針がある。そこでは、「同国は、...資源が豊富であり、...農業開発の余地も大きく、...人口の大多数が農業に従事しているが、その大部分は生産性の低い零細な生産活動にとどまり、...企業活動は未発達である」とされており、「回廊と周辺地域を結ぶ道路・橋梁改修やナカラ港の整備・電力等のインフラ整備を支援するとともに、...(プロサバンナ事業)により、農業開発支援に積極的に取り組み、包括的な回廊開発支援を行う」とある。
要するに、外務省は古典的な近代化の視点から同国を「途上国」と認識しており、生産性を高め、インフラ整備し、輸出振興して国の経済を大きくするためには企業活動の発達が不可欠、という考え方だ。プロサバンナもここに位置付けられている。そして、その包括的な青写真が「ナカラ回廊開発計画マスタープラン」である。筆者が委員をしている「開発協力適正会議」で同地域の電力配電網計画を検討した時、外務省幹部から次のような発言があった。
「日本企業のビジネス環境整備のためのインフラ整備という観点から、日本企業の関心が高い地域・分野を対象に、案件の形成を目的に戦略的マスタープランの策定を進めている。」(第19回2014年12月16日)
この会議は、国益論者の委員が多いこともあって、それに誘引されて外務省もJICAも本音を語ることが多い。他国に負けずに日本企業にいかに受注させるか。ODAの評価も、そこを中心に論じられる。別の会合でも、外務省はインドにおける高速鉄道(新幹線)事業獲得競争で中国に勝ったことに熱弁をふるっていた。
【No.319 TPPは日本と海外の市民をどこに導くのか (2016年1月20日発行) に掲載】
7月にモザンビーク最大の小農組織UNACのメンバーが来日し、8月は3週間強に渡る現地調査を実施した。9月にはモザンビークより元農業副大臣・現プロサバンナ担当一行が来日し、意見交換の場を持つなどしたが、今回は調査中の出 来事から「事業の成果」について考えてみたい。
「役に立つ」支援への不満?
乾期だというのに、目の前に広がる緑あふれる見事な畑。モザンビークで訪ねた農民組織の共同畑だ。5ヘクタールの畑の真ん中に貯水池があり、水路が畑中に張り巡らされている。数年前に農民らが手で掘ったという。土曜日の朝 早くなのに、すでに男女合わせて10人を超えるメンバーが熱心に作業をし、小さな子どもたちも遊びながら手伝っている。
昨年この農民組織にプロサバンナ事業より電動水ポンプが貸与され、種が提供された。今年4月の調査で、この組織のリーダーに話を聞いた際、事前の合意にもかかわらず、自分たちが希望していたものとは違う種が遅れて配られ、満足いく生産ができず、水ポンプ代が返せない可能性があるとの不満と不安を話していた。
今回はその後の話を聞いた。今年の種は、担当官と交渉し、自分たちが店で購入したために問題はなかったという。また、電動水ポンプには、一定の速度で早く水を畑に廻せる利点がある(「それで生産性があがったか?」との問いに回答はなかったが)。要は「それなりに役に立っている」とのことだった。だが、農民らが強調したのは、次の一言だった。「プロサバンナは私たちの話をまったく聞かない」
【No.318 アジアにおける外部環境の変化のなかでJVCは何ができるか (2015年10月20日発行) に掲載】
プロサバンナ事業に対し、これまでその事業内容の改善だけではなく、事業策定プロセスへの小農の「意味ある参加と対話」を求めて活動してきたが、3月末、プロサバンナ事業の青写真となる「マスタープラン」の「ドラフト・ゼロ」なるものが突如として公表された。そして翌4月に、この200ページ以上におよぶ文書に対して「小農たちの声を聞く」ために、小農や市民社会が準備時間を取れないほど直前の連絡の後、「公聴会」が実施された。私も急遽現地に飛んで参加したが、そこに小農たちの意味ある参加はなかった。※注①
日本の畑を歩くモザンビークの研究者
6月半ば、プロサバンナ事業の「マスタープラン・ドラフト・ゼロ」に関する公聴会の「やり直し」を求める声明を現地NGOらとともに出した、モザンビークの「農村モニタリング研究所(OMR)」のジョアオン・モスカ教授が緊急来日した。モスカ先生は、同国の農業・農村開発の研究に40年間携わっている。一週間弱の滞在期間に、研究会や議員訪問、NGOとの会合などが詰め込まれているなか、千葉県成田市三里塚を2時間だけ訪問することができた。この短い訪問を、「わんぱっく野菜」を運営される有機農家の石井恒司さんが、ご多忙ななか、快く受け入れてくださった。
【No.316 軍事優先の思想への対置として国境を超えた市民協力を (2015年7月20日発行) に掲載】
ODA のプロサバンナ事業に関する連載。前回は今年8月に現地を訪問しJICA と同行した高橋による報告だったが、今回は同じタイミングで農民たちの話を聞き取ってきた渡辺による報告だ。前回の報告と合わせてお読みいただきたい。(編集部)
政府・企業からの「圧力」
十月下旬、八月に一緒に現地調査を行なったプロサバンナ事業対象ナンプーラ州の農民組織UPC-Nの代表と首都マプトのNGO、ADEORUスタッフから連絡を受けた。ADEORUが調査で得た情報に基づきプロサバンナ事業の実態についてのプレスリリースを発表したところ、事業と契約している現地企業が「書かれた内容は間違い」だから「先のプレスリリースが間違いだったとする新たなリリースを出すよう」伝えてきたという。UPC-Nには政府関係者が訪問し、プレスリリースの内容の事実確認と「話を聞いた農民の写真を渡すよう」言われたそうだ。このことは企業や政府からの「圧力」として現地では受け止められている。
八月の調査では、農民たちを訪問した際、その多くで話の前にまず畑を一時間以上歩いて見せてもらい、その後一時間以上かけてゆっくり話を聞いた。彼らが連れていってくれたのはプロサバンナ事業下にある畑ではなく、これまで地道につくってきた畑だ。農民同士が語らうような場となったことで(ADEORUスタッフも農家の出身)、さまざまな本音がポロポロと出てきた。その結果、プロサバンナ事業が地域の人々の実情を包括的に捉えておらず、すでに実地で進められている「モデル普及」事業※注①がモデルとしてまったく機能していないことなど、事業の様々な課題が明らかになった。
今回の訪問先のひとつには、「モデル普及」事業における契約企業で、近隣の農民と契約栽培を行なっているMatharia Emprendimento 社( 以下ME社)がある。訪問の最中に、このME社が「農民を追い出し、土地を奪った」という話を聞き、実際に土地を追われたという農民たちに急遽話を聞くことにした。また、同企業と契約栽培をしている農民組織のメンバーや企業に雇用されている労働者にも会った。そこで語られたのは、不公正な契約栽培、モザンビークの最低労働賃金(月約一万円)を下回る形(月約三千円)での雇用状況、そして土地を追われ、新たな地で「生産する気を失った」という農民たちの声だった。
【No.313 今も続く紛争、その中で何を目指すのか (2014年12月20日発行) に掲載】
JVC に入って、気付いてみたら約10 年になります。2006 年に小学生になったばかりの息子のことをこの『ひとりごと』欄で書きましたが、今回は今年中学1年生になった娘について書きたいと思います。
娘は、私にも妻にもなぜか似ず、とてもまじめで何事にも手を抜かない性格です。中学に入った際、「まじめな先輩が一番多かったから」という理由から娘は吹奏楽部に入りました。そして、本人の希望と選抜試験を経て、トランペットを吹くことになりました。息子はサッカー部でしたが、そちらよりも吹奏楽部のほうが「ザ・体育会系」で、肺活量はじめ体力も使い、練習時間が長く大変です。夏休みも練習が厳しく、「勉強する時間がもてない」と悔しがり、中学生の頃なんてそこそこしか勉強していなかった私を不思議がらせています。
夏くらいになると、発表会も増えてきます。きちんとしたコンクールで吹くこともありますが、それよりも小中学校や地域のイベントに呼ばれて演奏する機会がかなりあります。数回しかまだ見ていませんが、あっという間にジブリ映画の曲をはじめ多くの曲を吹いていました。親バカと言われるでしょうが、素直に「すごいな~」と思いました。「数ヵ月前に始めたばかりなのに、こんなにできるなんて」と。近所の公園や駅前広場でトランペットを吹く娘をみて、私自身(これまでJVC でどれだけのことができてきただろうか...)と自問したところ、「まだまだですね」という答えを聞こえた気がしました。
【No.313 今も続く紛争、その中で何を目指すのか (2014年12月20日発行) に掲載】
パフェ、ケーキ、ジュース、チョコレート、果物、かぼちゃ、さつまいも、 栗...。これらがあれば生きていけるくらい、私は甘いもの好きです。逆に、砂糖なしのお茶やコーヒー、ピーマン、お酒などの苦いものが好きではありません。飲み会ではあっという間にお札が消えてしまいますが、いつも(そのお金があったらケーキバイキングに行けるのにな...)と思います。
以前私がいた某国のケーキやチョコレートのまずかったこと! パンはスカスカで、フレンチトーストにしようと液に浸けたらパンが溶けてしまいました。「日本に帰国したらケーキバイキングだ!」と想いは膨らんでいったのでした。ところが、2年数ヵ月経って日本に帰ってみると、私の胃はすでに甘いものをたくさん食べることを受けつけなくなっていました。結局ケーキバイキングは行かずじまい...。ただ、舌は今も甘くておいしいものを好んでいます。
【No.316 軍事優先の思想への対置として国境を超えた市民協力を (2015年7月20日発行) に掲載】
JVC に入職して、通勤が横浜から1 時間半の「長旅」となりました。オフピーク通勤であることと、関内駅からの乗車で混む前の京浜東北線という絶妙な組み合わせで、ほぼ座って通勤することができますが、ただ座っているわけではありません。席を譲ることを前提に席につかせていただきます。これすなわち「譲り道( ゆずりどう)」。
いつ、誰に、どのタイミング席を譲れるか。これがなかなか難しい。妊婦マークを付けてくれていると助かりますが、「的な人」も結構いらっしゃるので、「ヒールが高いので多分違う」など総合的な判断を求められます。譲りたいけれど遠くて、なんとかこちらの譲る気持ちを目ヂカラで訴えたりもします。見返りはもちろん求めていませんが、「ありがとう。すみませんねぇ」など声をかかられるとやはり嬉しいし、アメやポケットティッシュをもらったことも。
【No.318 アジアにおける外部環境の変化のなかでJVCは何ができるか (2015年10月20日発行) に掲載】
今回は再びプロサバンナ事業をとりあげる。7 月にモザンビークで開催された国際会議に参加した渡辺が、そこでの議論を通して感じた「音のない戦争」。それを止めるためにはどうすればいいのだろうか。(編集部)
分野を超えた反対へ
六月二日、モザンビークにおいて「No! to ProSAVANA」という全国キャンペーンの開始が発表された。キャンペーンにはナカラ回廊地域の小農および小農組織連合であるUNAC、女性フォーラム、人権リーグ、環境団体など分野を超えた八つの全国組織が参加している。
プロサバンナについて語る際、よく聞かれる質問がある。「日本企業やプロサバンナ事業は土地収奪を起こしているのか?」である。モザンビークでは本誌でも報告してきたとおり、海外投資企業による土地収奪はすでに頻発している。一方で、確かに日本企業による直接的な土地収奪はこれまでに報告されていない。であるならば、なぜ当地で全国キャンペーンが張られるほどの反対にあうのだろうか。
【No.311 市民に押し寄せる紛争や分断の波 (2014年8月20日発行) に掲載】
今から30 年以上前、地方から出てきたばかりの貧乏な学生だった頃、たまたま地図を見ていて、当時住んでいた世田谷のアパートの前を通っている水道道路(地下に水道管が通っている)をたどって北東方向にまっすぐ進むと、高円寺をぬけて当時友人の住んでいた中野駅近辺までたどり着けそうではないか、と気づきました。
その距離わずか(?)8kmあまり、1kmを15分で歩けば「2時間あれば友人宅に遊びに行ける」と思い、歩きました。どういう訳かまったく苦痛とは感じず、単純に達成感のみが得られたのです。
このような嗜好は今でもまったく変わりません。数年前には、自宅付近を流れる川沿いに北上して某ショッピングセンターまで歩きました。真夏の炎天下、途中で購入したペットボトルで水分を補給しながら、途中での昼食時間を含め、なんと往復で7時間半! この時の目的は、もちろん「買い物」です。
【No.312 変わりゆく風景と暮らし (2014年10月20日発行) に掲載】