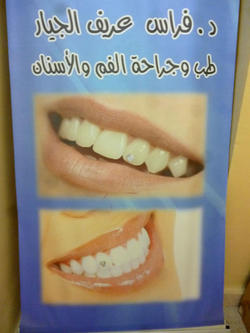パレスチナ最新情報
こんにちは、JVCエルサレム事務所の山村です。
2018年3月30日、パレスチナにおける「土地の日」からガザで始まり、西岸でも行われた難民の帰還を求める大規模抗議デモ「帰還の大行進」は、イスラエル建国による難民発生を記憶しパレスチナ側で「ナクバ(大惨事)の日」と呼ばれる5月15日まで続き、その後も小規模で続けられています。
5月14日の1日だけでも、デモへの参加者は4万人にのぼるとされています。イスラエル側による銃撃等で、この日の死者は60人を超え、封鎖の影響により病院で医薬品や設備が不足しているために負傷者は適切な処置が施されず、手足の切断を余儀なくされるケースも多く出ています。国際社会からの非難が集まっているのにもかかわらず、イスラエル側は武力による鎮圧の手を緩める気配はありません。
この人道的に見過ごすことのできない状況に対し、JVCと東エルサレムでの活動を共に続けてきた現地NGO「パレスチナ医療救援協会(PMRS)」が即時報告をリリースしました。 5月14日付で届いたその報告内容をご紹介したいと思います。
こんにちは、JVCパレスチナ事業担当の並木です。
2018年3月30日、パレスチナにおける「土地の日」から、特にガザで大規模なデモが続いています。イスラエル建国記念日まで毎週末に必ず行われ、難民の帰還を求めるこの抗議運動に対し、イスラエル軍はイスラエルとガザの境界線に近づいたデモ隊を実弾・ゴム弾・催涙弾で排除し、多くの死傷者が出ました。「報道関係者」のベストを着たパレスチナ人ジャーナリストまでも銃撃によって殺されています。
この状況に対し、私たちが東エルサレムでの活動を共に続けてきた現地のNGO「パレスチナ医療救援協会(PMRS)」が、声明文を送ってくれました。4月8日付で届いたその声明の内容をご紹介したいと思います。
最近、私たちJVCが日本で販売している刺繍製品の納品点検を行うため、ベツレヘムに位置するアッザ(ベイトジブリン)難民キャンプの中にある刺繍グループの方の家を、久しぶりに訪れました。
その時の彼女たちとのやり取りの様子を少しだけ紹介します。
今回は、皆さんにガザの女性が書いた文章「Even Money Won't Buy You a Good Life In Gaza(ガザではいくらお金があっても良い生活は送れない)」を紹介します。
「ガザではいくらお金があっても良い生活は送れない」
もしあなたに沢山のお金があって、そしてこの世界でガザ地区以外の場所に住んでいたとしたら、何をしますか?
答えを予想してみます。世界中を旅しますか? 最新の車を買いますか? 素敵な家を建てますか? それとも真に愛する人と結婚しますか? 世界中の食事に困っている人々を助けますか? 高級でお洒落な服を着ますか? 世界最高峰の大学で勉強しますか? 最新技術を用いた機器を買いますか? 全ての夢が叶いそうですか?
一人のガザに住むパレスチナ人の若い女性として、私にはそのようなお金は必要ありません。お金持ちになりたくないからではありません。ガザに住んでいる限り、お金が沢山あっても何の意味もないからです!
「パレスチナの男性は基本的に日本人でいうと中2くらいの感覚だよ!」
こういったことを現地にいる日本人女性の間で話すことがあります。その理由はと言うと、20代半ば頃になってもとにかくエネルギッシュでやんちゃな印象があるからです。例えば、パレスチナでは車に若者たちが何人も乗って騒ぎ、外国人である私たちに「ニーハーオ!」(中国人だと思い込んでいる)などとヤジをとばしてくる光景をしばしば見ます。また、JVCの旧事務所の裏は広い駐車場でしたが、毎晩若者たちがドリフトをしに来ており、大音量で車のブレーキの音が鳴り響き渡っていました。20時頃になると「あー今日も始まったよ」といった感じでした。来てばかりの頃は、道を歩いていると都度大声で話しかけてくる彼らのエネルギーにたまりかね、「もう、うるさい!!」と言ってしまうこともありました。コミュニケーションの垣根の低い中東文化もあるとは思いますが、それにしても一体どうしてパレスチナ人たちは何歳になっても少年ぽさが消えないのだろう、と日頃からとても疑問に思っていました。それはパレスチナ人の男性の友達ができても変わりませんでした。日々考えているうちに、そのヒントは彼らの子ども時代にあることに気づきました。
こんにちは。エルサレム駐在員の山村です。
エルサレムに来てから1ヶ月ちょっとの時、地元の歯医者に通うという何とも貴重な経験をしたことについてのお話、第二弾です。
翌日、恐る恐る昨日もらった名刺の番号に電話をし、歯医者の予約をしたい旨を伝えると、流暢な英語で「今日は~時までやっているよ。その時間までならいつでも対応するから、来られる時に来なさい。」と、落ち着いた声の男性が話してくれました。「これは期待できる!」と藁にもすがる思いで仕事終わりに歯医者へ向かいました。
その歯医者はいつも通勤で通っている大きな通りから少し中に入ったビルにあり、大きく看板も出ておらず、何とも地味な場所にありました。影にある雑居ビルの中に入ると、一室に歯医者らしき看板が・・・!ブザーを鳴らすと扉が開き、小さな待合室が現れました。確かに皆待っているのはパレスチナ人で、外国人の私が急に入って来たことに驚いたのか、受付の女性も含めて驚きの表情で迎えられました。日本のようにオルゴールの音などはない、なんともさっぱりした待合室で少し待つと、名前が呼ばれて診療室へ通されました。小さな、しかし清潔で新しそうな診察室の中に診療台は一つだけ。そしていかにも頼れそうで実力のありそうな風貌の先生が現れました。「私はあなたにかけましたよ・・・!」と心の中で思い、あたりを見渡すと、壁にはたくさんの国際会議へ出た証書がかけてありました。その中にはエジプトのカイロ大学歯学部の卒業証書もあり、「きっと大丈夫に違いない・・・!」と、安心して治療を待ちました。
先生は軽く歯を見て、「うーん。歯の神経が死んでいるかも知れない。今からレントゲンを撮ってきて」と、言われました。ショックを受けつつレントゲン技師がいる下の階の一室へ出向くと、ドアも締めずにレントゲン撮影がおもむろに始まり、その場で撮影代の20シェケルを支払い、レントゲンの結果はその場で一つ上の階にいる先生にデータで送信されました。先程の診療室に戻ると、先生がスマホでレントゲンの結果を見て(なんてハイテク・・・!)、一言。「君の前歯の神経は残念ながら死んでいる。ここ、黒い部分、見えるだろう?あまり時間がない。根管治療というものをやることになるけどいい?神経をとらずに保存するにはこの方法しかないんだ。君にはもう選択肢がない。」
衝撃の宣告です。急に歯が死んでいるなんて、しかも選択肢が私にはないなんて・・・。先生が「今やる?今度にする?まあ今日の分は10分で終わるよ。」というので、その場で治療を受けることを即決しました。麻酔の注射も打ち、高い技術がいる施術で、それなりに出血もしたのですが、先生は同じ部屋にいる同僚と話をしながら、また時々家族と電話で話しながら治療を無事終えてくれました。(頼むから集中して~と思う私は間違っているのでしょうか・・・)やはりパレスチナ人、歯の治療の最中も助手や電話の先の相手とペチャクチャ話していました。「帰りにトマト買ってきて」といった内容のやり取りを家族としていたように聞こえました・・・。一番私を心配させたのは、同じ部屋にいたもう1人の歯科医の態度です。必死に死にそうな歯に対する救出劇が繰り広げられている横で、コメディドラマを見ながら「アハハ・・・!」と笑っていたのです!ねえ、それ、今見る必要ある・・・?こっちは真剣なんですけど・・・!と思いながら、彼は無視しながら治療に専念することにしました。
もろもろ不安要素はありましたが、先生の腕に狂いはありませんでした。実は矯正もしていたせいで歯科医院への通院歴の長い筆者ですが、日本の歯科医の腕と比較しても全く劣っていなかったと思います。
治療が終わると、先生からこの治療は全三回、毎週月曜日の同じ時間に通えば終わること、全部で12000円かかることを告げられました。歯の治療は日本の保険が効かないので高いのですが、高度な技術のいる治療だったにもかかわらず、思ったよりも安く済みました。
三回治療に通い、最後にアイザリーヤの歯医者に行かされそうになった話を先生にしてみると、先生は次のように答えました。「それがパレスチナの問題なんだ。ここは色々と困難が多いんだよ。同じレベルの医療をどこでも受けることができない。エリアによって大きなギャップがある。ここはエルサレムだからイスラエル側にもパレスチナ側にも登録されていてレベルが保証されているから安心してもらっていいけどね。ここは技術は全くイスラエル側と変わらないよ。それに向こうより安いしね」
先生が使っていた接着剤はなんと日本のものでした。「日本のものはいいよ、日本のものはなんでもいい!きみの国はなんでもあるよね」と、made in Japanを愛用している様子でした。もう二度と歯科医にかからないように歯のケアには気をつけよう、と気を引き締めると同時に、また何か歯に一大事が起こっても、この先生がいるなら安心だな・・・と甘えてしまいそうな自分がいました。ただ、お金があるパレスチナ人はこうしてきちんとした歯医者に通えますが、お金のない家ではペンチで虫歯を抜くしか無いとのこと。そこに信頼できる医療があるのに手が届かない・・・やはりパレスチナの中でも貧富の差が大きいことを日々実感します。きっと最初に著者が連れていかれた研修医のところも、お金がない人たちにとっては歯を抜く、以外の唯一の選択肢かも知れません。
パレスチナでの支援活動、パレスチナからの発信は、市民の皆様からのご寄付に支えられています。郵便局やクレジットカードなどで、ぜひご協力ください。現在は、特にガザ地区での子ども栄養失調予防事業のための資金が足りない状況にあります。現地のためにお預かりし、大切に使わせていただきます。
※寄付はこちら(https://www.ngo-jvc.com/jp/perticipate/fundraise/)からお願いします。入力画面で募金先を「パレスチナ」にご指定ください。
こんにちは。エルサレム駐在員の山村です。
エルサレムに来てから1ヶ月ちょっとの時、地元の歯医者に通うという何とも貴重な経験をしたので、遅れ馳せながら皆さんに共有させていただきたいと思います。
それは春めいてきたある日、パレスチナ人のおたくでシロップ漬けのケーキをもらって食べていたとき、「これはまずい・・・」と自分の中で確かな危険信号を感知しました。前歯の様子がどうもおかしいのです。あたたかいものを食べても冷たいものを食べても前歯がズキッと染みるのです。「これは疲れからくるもので、ひょっとして少し我慢していたら良くなるかも・・・?」と自分を騙し、数日が経過しました。しかし、日に日に痛みが強まり、私の頭の中は、歯の痛みに始終占拠されることとなりました。「そろそろ歯医者に行かないと大変なことになる!」と、重い腰を上げたとき、ふと、パレスチナ側の歯医者はどうなっているのかしら?という疑問がわきました。小さな子どもでもたくさん虫歯があるのをよく見るけど・・。ただ、歯列矯正をしている人たちは沢山見かけるのです。ここまで教育レベルの高い人たちなので、きっと優秀な歯医者もいるに違いない・・・!というわけで、周りの外国人たちが「歯医者はさすがに医療設備の整っているイスラエル側で済ませたら?」とアドバイスをくれる中、パレスチナ側で歯医者を探すことにしました。
まずは、「歯が痛いんだけど・・・」と知り合いのパレスチナ人に相談してみると、そこにたまたま居合わせたパレスチナ人のおじさんが「じゃあ俺がアイザリーヤの歯医者に連れていってやる。エルサレムの歯医者は高くてしょうがない。安くてもそれなりの質のある歯医者があるから!明日○○時に集合!」と言うので、その次の日に彼と合流し、アイザリーヤ(JVCのプロジェクト地もあります。分離壁のヨルダン側西岸側・壁の内側・東は入植地、西と北は分離壁で分断されています)の歯医者に乗り合いバンで30分ほどかけて到着しました。すると、おじさんが急にバスを降り、とあるビルの一室にある歯医者めがけて一人走り出したかと思うと、すごい勢いでビルから戻ってきました。「もうやってない!帰るぞ!」と言うのです。「え!来たばかりなのに帰るの?しかもまだ午後の3時だよね?(しかもなんで朝に確認して来ないの・・・)」という私の質問をよそに、「また出直すぞ!」ということでまた同じ乗り合いのバンに乗って帰宅しました。
ちょうどその日に別の、いつも仲良くしているパレスチナ人姉弟のお宅にお邪魔して、ご飯を食べながら今日起きた出来事を説明すると、「歯医者に行ったら午後3時に閉まってたですって・・・?アハハ、それってあれね。研修医の実験台として安く治療が受けられるところじゃない?紹介者にもお金が入るから連れて行ったんだと思うわよ。危なかったわね、閉まっててよかったじゃない!アハハ・・・。」と、言うのです。私が真っ青になっていると、「ここが私が東エルサレムで通っている歯医者さん。とっても腕がいいし、あなたの事務所からも近いわよ。明日友達が行くって電話しておくわね。」と、東エルサレムにある歯医者の名刺をさっと渡してくれました。持つべきものは"信頼できる地元の人!"と、このときほど思ったことはありません。
(第二回につづく・・・)
パレスチナでの支援活動、パレスチナからの発信は、市民の皆様からのご寄付に支えられています。郵便局やクレジットカードなどで、ぜひご協力ください。現在は、特にガザ地区での子ども栄養失調予防事業のための資金が足りない状況にあります。現地のためにお預かりし、大切に使わせていただきます。
※寄付はこちら(https://www.ngo-jvc.com/jp/perticipate/fundraise/)からお願いします。入力画面で募金先を「パレスチナ」にご指定ください。
【7月時点で、現在育休中の並木が執筆した記事です。】
こんにちは、東京担当の並木です。
実は、4ヶ月後に出産を控えた私。お腹の中には双子の女の子がいて、無事に生まれれば我が家は3姉妹になります。
現地のパートナーNGOのスタッフたちは、連絡をするたびに「お腹の双子の成長はどう?」「娘さんは元気?」と仕事そっちのけで(!)質問の嵐。こちらは「妊娠7ヶ月目だけれど、もうお腹がはち切れそうよ(笑)」と答えながらも、遠い私のことをパレスチナから気遣い、子どもを何よりも大事にする彼らの温かさに、私も改めて人間関係の在り方を考えさせられます。
ガザで一緒に事業を進めている「人間の大地(AEI)」のプロジェクトコーディネーター、アマルは、去年結婚した息子さん夫婦に待望の男の子が生まれるのだとか。「こっちは9月に生まれるのよ」と心底楽しみな様子で、「あなたの娘と1ヶ月違いよ。大きくなったら結婚させるのはどう?(笑)」と気の早い打診。
「そうねぇ、まずは娘たちをガザに連れて行かなきゃ(笑)。20年後かしら?」と答えたところ、「あら、ガザだと結婚は早いのよ。16年よ、16年後!」とリアルな数字が返ってきました。
16年後。ガザは、どうなっているのでしょう。
ガザの封鎖が始まったのが2007年で、今年でちょうど10年です。10年でここまで状況が悪くなるなんて、一体誰が考えていたでしょうか。
この10年で、ガザからは輸出が出来なくなって産業は荒廃し、12万人の雇用を誇った製造業は7,000人ほどしか雇えなくなってしまいました。人々はガザを出てイスラエル側で働くこともできず、東京23区よりも狭いガザの中をぐるぐると回るタクシー運転手の月給は、良くても500ドル程度。10年前の3分の1以下だ、と運転手のおじさんたちは嘆いています。毎年1.8万人もの学生たちが、仕事が決まらないまま大学を卒業していきます。若者たちの半数が、ガザから出て行くことばかりを考えているといいます。
そして2014年の戦争開始から、今月で3年が経ちました。「これ以上、状況が悪くなることはない」と信じて生活を築いてきた人々の僅かな希望を裏切るように、今のガザでは電気も水道も使えない状況が本格化しています。ポンプが使えず、人々は身体を洗う水もわざわざ買って運び、下水も流せずに家に溜めていると聞きました。パレスチナの人々は概して清潔好きですが、このままでは病気が流行してしまうかもしれません。
そんな状況の中でもなお、「16年後、お見合いさせましょうね!」と冗談まじりの夢を語れるアマルやガザの人々。まだ生まれてもいない娘たちには悪いものの、その夢が何だか一筋の光のようで、「16年かぁ......」と少々本気で考えてしまう私です。
私の子どもたちも、ガザの子どもたちも、まずは無事に生まれてきますように。そして、あと16年で私たちは、ガザに衛生とインフラを取り戻し、封鎖を解除して、安全な普通の街と暮らしを創り直さなければなりません。
16年と言わず、今すぐにでも。そのためには、もっとたくさんの人たちとこの問題を話し合い、決定権のある人々の心と手を動かして、一つひとつの障壁を取り除いていかなければならないのでした。
こんにちは、話題沸騰のエルサレムに住み始めて5ヶ月目になりました、現地駐在員の山村です。こちらでは連日中東らしい暑さが続き、汗を大量にかきながら「ショーブ、ショーブ(暑い、暑い)」というのが挨拶代わりになっている毎日です。
蜂蜜100%のキャンディーが好きで、パレスチナ駐在中にも日本から持参していた。疲れた時に頬張るのだが、最近は食べるたびに、あるガザの姉弟のことを思い出してしまう。
2016年11月のある日、一人でのガザ出張を終えた日のこと。ガザとイスラエルを隔てるエレズ検問所を出て、イスラエル側で迎えの車を待っていた私のところに、同じくガザから出てきた小学生くらいの姉弟がやってきた。病人でもない親子の姿をエレズで見るのは本当に珍しく、初めてだった。誰かの結婚式にでも参加するのか、可愛くおめかしをしてはしゃぎ回っている。同行するのは大人の女性3人、祖母と母と叔母で、汗を拭きながら人数と同じ数だけの大きなトランクを何とか引きずっていた。
姉弟が、無邪気に話しかけてきた。「あなたはどこへ行くの?」
「ガザで仕事を終えたから、エルサレムの家に帰るんだよ」と答えると、彼らは「エルサレム! 私たちのエルサレムは綺麗なところでしょう?」と『パレスチナの首都』を語って得意げだ。人懐っこくて可愛らしかったので、私はポーチにしまっていた蜂蜜のキャンディーを5個取り出して、「皆で食べてね」と渡した。「ありがとう」とはにかんだ笑顔で受け取った姉弟は、それを握りしめて女性たちのところに駆けて行く。
ところが、その姉弟が今度は「水、水は持ってない?!」と駆け戻ってきた。どうやら飴が甘過ぎたようで、向こうの方では女性たちが「喉が渇いた!」と訴え、水を探している。要らないおせっかいだったらしい。
近くのドライバーからイスラエル製のペットボトルの水を貰い、回し飲みする女性たち。飲んだ後に、何だか顔をしかめている。姉弟も水を受け取って飲むなり、「うえっ、まずい!」と大げさなリアクション付きの大きな声で言い放った。
「知ってる? イスラエルのものは、何でもまずいんだ。この水だって、まずいだろ? ガザとは比べられないよ。食べ物も飲み物も、パレスチナのほうが絶対に美味しい」
手の甲で口を拭いながら、弟の方が私に熱心に訴えてきた。美味しいだろうか。私には、分からない。
それでも、この子たちの物心がつくころから、ガザはイスラエルによってずっと封鎖され、3回の大きな戦争を経験してきた。「ガザの人間だから」という理由で彼らに課された、10年にもわたる集団的懲罰。何千人が殺されても、何万人もが大切な何かを奪われても、イスラエルからの謝罪は無い。どこの誰が殺されたとか、誰が職を失ったとか、悪いニュースばかりが続く。状況も一向に改善されることがなく、その底には個々人の涙ぐましい努力ではどうしようもない政治・経済情勢が横たわり続けている。
小学生にも染み付いた、『あっち側』と『こっち側』を明確に区別し差をつける視点は、その中で養われてきたのだろう。その重みを考えると、私が見たものに基づいて何かを言い返したい気持ちは、全く湧いてこなかった。
「ガザの外に出たけど、ガザには戻る予定なの?」そう聞くと、お姉ちゃんが「ううん、戻らない」と小さな声で、けれども即答した。「本当は戻らないといけないんだけど、戻りたくないの。ガザで何が起こっているか、知ってる? 子どもだって、殺されるのよ。危ないの。だから、これから西岸で暮らすの。西岸の学校に通うのよ」
やがて、女性たちとタクシードライバーの料金交渉が終わったらしく、子どもたちの名前が呼ばれた。「またね!Facebookに、『プリンセス』って名前で登録してるの。探してね!」と言いながら、姉弟は駆けて行った。
世の中には「プリンセス」が多すぎて、その後は彼女たちと連絡を取れていない。子どもらしい日々を送っているだろうか。ガザの水のように汚染されてはいない西岸の水を飲み、ガザのように停電を気にせずテレビアニメを見ているだろうか。
そうであってほしいな、と願いながら、ガザ人口200万人の半分を占めるという子どもと若者の暮らしを思う。集団的懲罰が終わらない限り、彼らがイスラエルのものを心から「美味しい」と言う日は、来ないかもしれない。