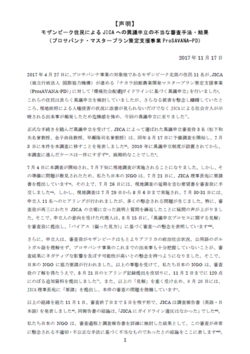声明の記事一覧
アフガニスタンでは、6月15~17日の3日間、アフガニスタン政府とタリバンの間で、これまで一度も実現していなかった停戦が実現しました。
政府側、タリバン側の兵士、人びとが歓喜し、抱き合って喜ぶという信じがたい光景が見られました。市民が間に立ち、政府とタリバン側の双方が平和に向けての意見を交わすという集まりがあったことも報告されています。人びとが平和を渇望していることは明らかです。
この停戦にあたり、JVCを含む日本のNGOは、アフガニスタンの人々ととに、あらためて、平和を希求し、アフガニスタンにおける停戦の延長、暴力の停止、和平プロセスの進展を求めます。
【7月3日追記:日・英声明共に賛同団体追加】
以下、共同声明をご覧ください。
日本のNGO共同声明:アフガニスタンにおける停戦の延長、暴力の停止、和平プロセスの進展を求めます
カレーズの会、シャンティ国際ボランティア会、
難民を助ける会、日本国際ボランティアセンター、ピースウィンズ・ジャパン
2018年6月22日
私たちは、アフガニスタンの人びととともに、アフガニスタンの支援に関わる日本のNGOです。私たちは、アフガニスタン政府とタリバンによる初めての停戦を歓迎し、それがもたらした平和への希望を人びとが感じることができた今、あらためて、アフガニスタンにおける平和を希求し、以下の要請をいたします。
停戦の延長について
私たちは、アフガニスタン政府とタリバンとの間で初めて実現した、このたびの停戦を歓迎いたします。また、これまで一度も実現していなかった初めての停戦にあたり、両者が様々な困難を乗り越えて停戦への決断を行ったことに敬意を表します。双方の兵士や一般の人びとが歓喜している場面が至るところで見られ、また、市民が間に立ち、政府とタリバン側の双方が平和に向けての意見を交わすという集まりがあったことも報告されています。人びとが平和を渇望していることは明らかです。私たちは、政府が、さらなる停戦の延長を表明したことを歓迎し、タリバン側にこれが受け入れられることを望みます。そして関係主体、関係国、日本政府を含む国際社会が、こうした動きを後押しし、停戦延長のためのあらゆる働きかけを行うことを要請します。
暴力の停止について
停戦による歓喜の一方で、停戦を祝う、もしくは関連する集まりを狙ったと思われる攻撃が行われ、市民を含む多数の死傷者が出ています。私たちは、亡くなられた方のご冥福を謹んでお祈りするとともに、ご家族や親族、友人の皆さまに心より哀悼の意を表します。私たちは、こうした暴力を非難し、ただちに暴力が停止されることを求めます。そして関係主体、関係国、日本政府を含む国際社会が、暴力停止のためのあらゆる働きかけを行うことを要請します。
和平プロセス進展について
私たちは現地の人びととともに、現地に根づいて活動に取り組む団体として、暴力によってもたらされるのが悲しみと怒りだけあるということを経験してきました。暴力で問題の解決をもたらすことはできません。このたびの停戦を機に、あらゆる紛争当事者が和平プロセスを進展させることを求めます。そして関係主体、関係国、日本政府を含む国際社会が、そのためのあらゆる働きかけを行うことを要請します。
アフガニスタンの人びととともに、平和を願ってやみません。
以上
- 【本声明についてのお問い合わせ先】
- 日本国際ボランティアセンター(JVC)担当:小野山亮、加藤真希
〒110-8605 東京都台東区上野5-3-4 クリエイティブOne秋葉原ビル6F
TEL: 03-3834-2388 Email:onoyama@ngo-jvc.net kato@ngo-jvc.net
(以下、英語翻訳版)
We request for extension of ceasefire, cessation of violence and progress on peace process in Afghanistan
22 June 2018
Association for Aid and Relief, Japan (AAR Japan)
Japan International Volunteer Center(JVC)
Karez Health and Educational Services (KHES)
Peace Winds Japan (PWJ)
Shanti Volunteer Association (SVA)
We are Japanese NGO engaged in the support of Afghanistan together with the people of Afghanistan. Welcoming the first ceasefire between the Government of Afghanistan and the Taliban, and as people were able to feel the hope for peace that the ceasefire brought about, we will continue seeking peace in Afghanistan and we request for the following:
About extension of ceasefire
We welcome the ceasefire which was realized for the first time between the Government of Afghanistan and the Taliban. We express our respect to the decisions made by both parties to achieve the first ceasefire which had never been realized before by overcoming various challenges. We could see soldiers of both sides and people delighted everywhere. It is also reported that citizens stood between the Government and the Taliban, so that both sides could exchange their opinions for peace. It is clear that people are eager for peace. We welcome the Government's announcement of further extension of the ceasefire and hope it will be accepted by the Taliban. We also request that those concerned, concerned countries and the international community including the Japanese Government will support this and take all the necessary actions to extend it.
About cessation of violence
While joys of ceasefire were observed, there were attacks seemingly targeting a ceasefire celebration and a related gathering, causing many casualties including civilians. We pray for the souls of those who have passed away and express our sincere condolences to their families, relatives and friends. We condemn such violence and demand immediate cessation of violence. We also request that those concerned, concerned countries and the international community including the Japanese Government will take all the necessary actions to stop violence.
About the progress of the peace process
As organizations working with people of Afghanistan, rooted in the community, we have experienced fist hand that violence brings about only sadness and anger. Violence cannot solve problems. Alongside the ceasefire of this time, we request to all parties of the conflict to make progress on the peace process. We also request that those concerned, concerned countries and the international community including the Japanese government will take all the necessary actions for the progress on the peace process.
We wish for peace with people of Afghanistan.
今年3月30日からガザで続く抗議活動「帰還の大行進」において、医療従事者やジャーナリスト、子どもを含むパレスチナ人が、イスラエル当局の実弾を含む攻撃により死亡・負傷しています。5月末日時点で1万3,000人以上が負傷し、128人が死亡しており、抗議活動に対して殺傷力のある武器を使用することについて、国際社会の批判が高まっております。
この状況に関し、パレスチナに関わるNGO12団体は本日、共同で以下の要請文を河野太郎外務大臣に提出しました。非暴力の参加者に対する殺傷力のある武器の使用を中止し、また国際法違反として非難されている事件の独立調査が行われるよう、日本政府の働きかけを求めるものです。また要請文の内容を直接協議できるよう、外務大臣との面会を要望しています。
(以下、要請文本文)
ガザでの抗議運動参加者に対する殺傷力のある武器使用中止の働きかけ、真相調査の調整に尽力してください
外務大臣
河野 太郎 殿
私たちはパレスチナにおいて、苦境の中に生きる人々への支援を続けてきた日本のNGOです。
現在、パレスチナでは、米国大使館のエルサレム移転が行われた5月14日を含む、2018年3月30日から続くガザでの抗議運動において、イスラエル当局の攻撃により128 人のパレスチナ人が死亡し、数百人の子どもを含む1万3,000人以上が負傷しています※注(1)。また同時期に211人の医療従事者が負傷し、25台の救急車が損傷しています※注(2)。この状況に対し、私たちは、日本国政府に対し以下のように要請します。なお本要請は、当地で活動する80以上の国際NGOによるネットワーク「AIDA」が5月15日に発表した声明"80+ INGOs Demand Accountability for Israel's Unlawful Killing of Demonstrators in the Gaza Strip※注(3)"に基づいており、同様の要請がNGOを通じて各国政府へと提出されています。またその結果はAIDAへ報告された上で、情報回覧および拡散されています。
- 非武装の参加者に対する殺傷力のある武器の使用を中止するよう、イスラエル政府に働きかけてください。
- また、国際法違反として非難されている本事件について、2018年5月18日に国連人権理事会で派遣が決定した独立調査※注(4)が滞りなく行われるよう、関係者の調整に尽力してください。
- 非人道的なガザの封鎖を一刻も早く解除するよう、イスラエル政府に働きかけてください。
国際法に基づけば、殺傷力のある発砲は人命への切迫した危機にさらされる状況下以外では使用されるべきではない※注(5)とされています。また医療従事者への攻撃は、日本もその締約国である「国際裁判所に関するローマ規程※注(6)」において戦争犯罪と見なされます。人間の尊厳を守るため人類が多大な犠牲を払って積み上げたこれら国際法が容易に破られることは、いかなる政治的理由によっても肯定されることではありません。よって今回のイスラエル当局によるパレスチナ人の攻撃は、真相を解明する調査が必要不可欠です。
またパレスチナ、とりわけガザの人々は、改善するどころか戦争や封鎖の継続を経てますます悪化する状況に絶望しています。エルサレムのイスラエルへの帰属を認めた「米国主導の和平」についても、人々は期待を失うだけでなくその一方的なプロセスを非難しており、また国連総会では事実上の非難決議が出されるなど、米国によるイニシアチブは求心力を失っています。
日本が支持する当事者間交渉を伴う和平プロセスの再開には、パレスチナ側の信頼を勝ち得る主体の参加が欠かせません。昨年12月から外相・首相による当地訪問を重ねてきた日本国は、当地をめぐる現在の情勢を沈静化し、和平を進める主導力となり得る独自的立場にあるといえ、人々の尊厳を回復し得る行動が、当地の人々からも求められています。
2018年6月7日
特定非営利活動法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク
特定非営利活動法人 APLA
サラーム・パレスチナ(日本聖公会 東京教区正義と平和協議会)
特定非営利活動法人 JADE-緊急開発支援機構
セーブ・ザ・オリーブ
公益社団法人 日本国際民間協力会(NICCO)
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター(JVC)
日本YWCA
合同会社 パレスチナ・オリーブ
特定非営利活動法人 パレスチナの子どもの里親運動(JCCP)
特定非営利活動法人 パルシック(PARCIC)
特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ
- ■この要請文に関する連絡先
- 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター(JVC)
〒110-8605 東京都台東区上野5-3-4 クリエイティブOne秋葉原ビル6F
TEL:03-3834-2388 / FAX:03-3835-0519 / E-mail:info@ngo-jvc.net
人道支援/平和構築グループ 今井、並木
※注(1) UNOCHAウェブサイト参照、5月31日時点(https://www.ochaopt.org/content/overview-may-2018 )
※注(2) UNOCHAウェブサイト参照、6月6日時点(https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-health-sector-struggles-cope-massive-influx-casualties-amid-pervasive-shortages )
※注(3) AIDAウェブサイト参照( http://www.aidajerusalem.org/80-ingos-demand-accountability-for-israels-unlawful-killing-of-demonstrators-in-the-gaza-strip/ )。日本語訳はJVCウェブサイトに掲載。( https://www.ngo-jvc.com/jp/projects/advocacy-statement/2018/05/20180522-aida.html )
※注(4) 国連人権理事会ウェブサイト参照。決議A/HRC/RES/S-28/1の主文5にて言及されている。( http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session28/Pages/28thSpecialSession.aspx )
※注(5) 国際連合人権高等弁務官事務所ウェブページ "Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials" (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx )主文9参照。1990年8月に開催された「第8回 犯罪防止・犯罪者の処遇に関する国連会議」にて可決され、同年12月の第69回国連総会でコンセンサスにて可決された決議A/RES/45/166にて歓迎された。(http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r166.htm )。
※注(6) 外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_1.html )
アメリカ大使館がエルサレムへ大使館を移転した5月14日、パレスチナ・ガザで行われた非武装のデモに対してイスラエル当局が実弾を使用し、61人が亡くなりました。この状況について、JVCも加盟する現地の国際NGOネットワーク「AIDA」が以下の声明を発表し、JVCも賛同し署名を行いました。
JVC理事の谷山博史と田中優が呼びかけ人として参加している「イラク戦争の検証を求めるネットワーク」が、イラク戦争開戦から15年となる今年、以下の声明を発表しました。イラク戦争への日本の関与、そして、その後の振り返りがなく今までに至っていること、決して「過去」のこととして忘れられてはいけない出来事です。ぜひ関心を寄せていただけましたら幸いです。
【以下声明本文】
今年の3月20日にはイラク戦争から15年になります。イラク戦争はアメリカやイギリスなど開戦した国々ですら「間違った戦争」と認めた戦争です。開戦の口実となった大量破壊兵器は見つからず、逆に内戦状態に陥り、IS(=イスラム国)が台頭するなど世界中にテロの拡散と混迷を招きました。イラクの人々は「テロ」と、それを撲滅するはずの「対テロ」の双方によって命を奪われ続けているのです。
あの時、日本はいち早く米英の開戦に支持を表明しました。世論の反対を押し切ってイラクへの自衛隊派遣も断行しました。なのに...日本では、開戦国ですら誤りを認めている戦争の大義について誠実な検証が行われていません。
現在、日本のすぐそばでも新たな戦争の開戦危機があります。アメリカと北朝鮮の攻撃的な言葉の応酬、脅威を煽るメディアはイラク戦争開戦前を思い起こさせます。
あの時、イラク同様、「悪の枢軸」と呼ばれた北朝鮮が核開発をすすめたのは、「安易に武装解除に応じて、イラクの二の舞になることは避けたい」という警戒感からだったのではないでしょうか。「大量破壊兵器の査察がまさか戦争にまで広がるまいと考え、それを素直にうけいれたことも(フセイン政権)の大きな失策だ」(2004年4月11日付 労働新聞)。
イラク戦争はたった15年前に日本が積極的に関わった戦争です。未来をつくるには過去の「失敗」から学ぶことが何よりも大切だと私たちは考えています。イラク戦争開戦から、15年目の3月20日、私達は以下のことを求めます。
- 以下の3点を検証する独立の第三者委員会を政府が設立し、検証結果やその過程を全て公開すること。
・「イラク戦争支持の政府判断に関する見直し」
・「自衛隊イラク派遣の判断の是非」
・「イラク復興支援への日本の関わり」
- 小泉純一郎元首相、川口順子元外務大臣、石破茂元防衛庁長官など、イラク戦争支持・支援した政権関係者らが、その判断や過程について、詳細を明らかにすること。
- イラク戦争の失敗から学び、北朝鮮の核とミサイル問題に対し、武力によらない平和的な解決へ、日本政府は全力を尽くすこと。国連憲章違反の先制攻撃やそれを容認するような発言を慎むこと。
2018年4月7日にシリアの東グータ地区において一般市民への化学兵器使用が疑われたことを受け、日本時間の14日、アメリカ合衆国、イギリス、フランスの三国はシリアのアサド政権に対する軍事攻撃を実施しました。
私たち日本国際ボランティアセンター(JVC)は、長年にわたってイラク、アフガニスタン、スーダン、パレスチナを含む中東諸国において、紛争で傷ついた人々に対する人道支援活動を続けてきました。またこれまでにも、米国とロシアを含む諸外国やシリア政府、武装勢力による軍事作戦で多くの民間人が犠牲になってきたことを憂慮し、武力の応酬が紛争の終結を遠のかせているとの認識に基づいて、懸念の声明を発表してきました。
このたびのアメリカ、イギリス、フランスによる軍事介入は、計画性や対象の限定に関わらず、民間人を巻き込み得る武力介入を避けるための外交努力、および国連安保理決議による正式かつ十分な過程を経ない行為であり、過去、イラクやアフガニスタンでアメリカなどが軍事介入の正当化事由とした"自衛権"も、当時と同様に到底正当化できるものではなく、明らかな国際法違反です。
今回の攻撃についても、下記のように要望します。
- 今回のような武力介入が、化学兵器使用に対する公式で中立な検証の実施の機会を喪失させるようなことがあってはなりません。化学兵器使用がシリア政府によるものだという確固たる証拠は、未だ開示されていません。攻撃を行うのではなく、化学兵器禁止機関および国連共同調査メカニズムの枠組みでの調査団派遣を実現させ、それをシリア政府が受け入れるよう国際社会が積極的に働きかけることを求めます。
- 日本政府には、今回の軍事攻撃の「決意を支持する」(4月14日首相談話)という立場ではなく、化学兵器使用に関する中立的な調査の実施をはじめ、武力介入ではない形での危機の打開に向けて国際社会で積極的な役割を担うことを求めます。
以上
この声明に関する連絡先
特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター(JVC)
〒110-8605 東京都台東区上野5-3-4 クリエイティブOne秋葉原ビル6F
TEL:03-3834-2388 / FAX:03-3835-0519 / E-mail:info@ngo-jvc.net
人道支援/平和構築グループ 今井、並木
(以下英語訳:日本国際ボランティアセンター・英語ボランティアチーム)
Statement on the military attack on Syria by the United States, the United Kingdom, and France
16 April 2018
Japan International Volunteer Center (JVC)
On the assumption that on 7 April 2018 chemical weapons were used upon innocent civilians in the Eastern Ghouta district of Syria, the United States, the United Kingdom, and France on 14 April 2018 conducted a military attack on the regime of Syrian President Bashar al-Assad. We, Japan International Volunteer Center (JVC), have undertaken humanitarian aid in such places as Iraq, Afghanistan, Sudan, and Palestine to aid local peoples suffering from conflicts. Having witnessed the serious harm inflicted upon innocent citizens by the military actions of countries such as the United States and Russia, as well as by the government of Syria and other military bodies, we have made statements emphasizing that military reciprocation only hinders peace and resolution.
The present military intervention by the United States, the United Kingdom, and France, regardless of the specified plans and targets, violates international law. This is because it does not abide by preceding diplomatic efforts to avoid interventions that may potentially harm innocent civilians, and it ignored the standard process of careful deliberation at the United Nations Security Council. It also lacks the justification of military action by the right to self-defense, which, for example, the United States insisted upon in the cases of the wars in Iraq and Afghanistan. We therefore appeal to the international community and the Japanese government as follows.
- The chance for official and neutral organizations to investigate the use of chemical weapons should not be forfeited by the present military intervention. No clear evidence is yet shown that the government of Syria used chemical weapons. We request an investigative team to be dispatched through the mechanisms of the UN and of organizations working to prohibit the use of chemical weapons, and we urge the international community to assertively call upon the Syrian government to accept the investigation.
- We request the Japanese government to not stand by its decision to "support" the military attack (statement by the Prime Minister, 14 April 2018), and instead, starting with a neutral investigation into the use of chemical weapons, play an active role in the international community to pursue solutions to the present crisis that avoid military intervention.
For any inquiry, please contact
Takaki IMAI or Mai MAMIKI
Humanitarian Aids & Peace Building Group
Japan International Volunteer Center (JVC)
Creative One Akihabara Building 6F, Ueno 5-3-4, Taito-ku, Tokyo 110-8605
TEL:03-3834-2388 / FAX:03-3835-0519 / E-mail:info@ngo-jvc.net
2017年12月、アメリカ、トランプ大統領が行った「エルサレムをイスラエルの首都として認定し、大使館を移転する」旨の発表は、国連総会が実質的な非難決議を可決する等、大きな波紋と反発を呼びました。この動きに対し、アメリカはさらにUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)への拠出金のほぼ半分を凍結、事実上削減することに踏み切りました。
JVCもメンバーの一員であるパレスチナのNGO連合「AIDA」は、この状況に対して以下のような声明を出しました。
激化しているシリアでの攻撃について、JVCも事務局として参加しているシリア和平ネットワークが、以下の声明を発表しました。
シリアの武力攻撃を直ちにやめてください。
2018年2月23日
シリア和平ネットワーク
私たちはシリアの紛争終結と和平実現に向けて、アドボカシー(政策提言)活動と確かな情報発信を実施していくために結成されたNGO、アカデミア、市民のネットワークです。
東グータにて、複数の部隊による武力攻撃が極端に激しくなり、爆撃と砲撃で、死者負傷者が250人を超えて増え続けていると報道されています。さらに、東グータでは6つの病院が攻撃で破壊され、何千もの人々が基本的な保健医療へのアクセスを失ったとの発表もありました。反体制派も首都ダマスカスに砲撃を行い、20日だけで13人の死亡が確認されています。
東グータ地方を含むダマスカス郊外県、デリゾール県南東部、イドリブ県南東部、アレッポ県西部や北西部(アフリーン郡)での無差別攻撃が激化しています。攻撃をしているのは、シリア軍、ロシア軍、イラン軍、イスラエル軍、アメリカ軍、トルコ軍、YPGに加えて、アル=カーイダ(シャーム解放委員会)とさえも共闘して東グータで戦闘を続ける武装勢力です。
8年目に突入しようとしているシリア紛争では、すでに多くの住民が死亡、重傷を負っています。
武力攻撃を行っているすべての人たちに伝えます。攻撃を直ちにやめてください。
これ以上の犠牲者を出さず、シリアを平和な国にすることは国際社会の担う責任です。停戦の手続きを直ちに始めて、人々の安全を確保してください。負傷者にはすみやかに治療の機会を提供してください。不幸にも家族を亡くした人たちには、大切な家族とお別れをする時間を作れるようにしてください。破壊された土地で住むところも食べるものもない人たちに支援が届くようにしてください。
日本政府には、上記に関して問題解決に積極的に取り組まれるよう期待します。
すべての人たちの努力で、シリアに和平がもたらされることを切に願います。私たちはそのために声を上げ続けます。
2018年1月24日、JVCの事務所もあるアフガニスタン東部ナンガルハル県ジャララバード市において、国際NGOのセーブ・ザ・チルドレンの事務所を狙った大規模攻撃があり、アフガニスタン治安部隊との戦闘が長時間続き、一般市民5名の方が亡くなり、6名の子どもを含む21名の方が負傷されたと報じられています。緊急速報は以下:https://www.ngo-jvc.com/jp/notice/2018/01/20180125-jvc-afghanistan.html
JVCも加盟する、アフガニスタンで活動する138の国内・国際NGOのネットワーク団体「ACBAR」(アクバル:Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development)はこの事態に対して、「ACBARはジャララバードにおけるNGOへの攻撃を強く非難する」という声明を出しており、JVCにて仮訳を行いました。下記、「ダウンロードできるデータ」よりご覧いただければと思います。
ぜひ、現地で起こっていることを知っていただき、さらにより多くの方への発信などもお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2017年4月27日、プロサバンナ事業対象地の地域住民がJICAへの異議申立を行いました。
その後、同申立に対する予備審査が行われ、7月3日、本調査に進むことが正式に決定しました。
これを受けて、7月21日に、JVCを含む日本のNGOは、審査が真に公正なものとなり、訴えた小農たちの想いを受け止めるものとなるよう、JICA理事長に要請書を提出しました。
しかし、11月1日に出された、審査役による調査報告書(審査結果)は、
そのプロセスを含めて非常に残念な結果となりました。
また、この調査報告書は日本語と英語で直ちに公開された一方で、ポルトガル語のものはまだ作成されておらず、申立人らは内容が確認できない状況に置かれています。(その後日本語版、英語版の公開から1ヵ月たった12月1日になって、ようやくポルトガル語の調査報告書が公開されました。)
これを受けて、プロサバンナの問題に関わってきたJVCを含む日本の5団体より抗議声明をJICA理事長宛に提出しています。
なお今後は、これらNGOにより審査のプロセスやあり方についての分析を行い、報告書を作成する予定です。
アメリカ、トランプ大統領の「エルサレムをイスラエルの首都として認定し、大使館を移転する」発表は、イスラエルの占領下に苦しむパレスチナ人だけでなく、国際社会において大きな反発を呼んでいます。これに抗議するパレスチナ人に対するイスラエルからの暴力的弾圧、ガザ地区に対する攻撃、空爆も連日続いています。
JVCがメンバーの一員であるパレスチナのNGO連合「AIDA」は、この状況に対して以下のような声明を出しました。
米国のエルサレムに関する発表に深刻な懸念を表明する
「米国がエルサレムをイスラエルの首都として認定し、大使館をエルサレムへ移転することは、パレスチナ人とイスラエル人の双方に大きく影響する軽率な行為である」とAIDA(占領下のパレスチナで活動する人道、地域開発、人権に携わる80以上の国際NGOの同盟)は表明する。
トランプ大統領の発表は、エルサレムをパレスチナの首都として同時に認めることを明らかに怠っており、バランスを欠いている。そのために、この発表は紛争の平和的で公正な解決に対して深刻な影響を及ぼす可能性が高く、占領下のパレスチナとイスラエルに住む人々が暴力に晒されるリスクを増幅させる。
AIDAは、この決定が、イスラエルの相次ぐ国際人道法、及び国際人権法の侵害を悪化させ、パレスチナ人が抱える現在の深刻な人道・開発における危機を増加させることになるだろうと考える。
同発表は、東エルサレムのイスラエルへの一方的な併合を実質上認めており、国際社会や国連安全保障理事会が一貫して反対してきた行為である。国際法上、東エルサレムは占領下パレスチナの不可欠な一部であり、米国を含む第三国は東エルサレムの不法な併合を認める行為-たとえそれが暗黙のものであっても-を全て避けるべきである。なお同発表は、暴力を伴う形で領土を獲得することを厳格に禁止する国際法に相反する。
AIDAは米国に対して、状況の悪化につながる更なる一方的な行為を取らないと同時に、恒久的な和平、そしてイスラエルにより50年間続いているパレスチナ占領と紛争状態の終結を促進するよう、呼びかける。
以上
(日本語訳:日本国際ボランティアセンター)
FOR IMMEDIATE RELEASE:
INGOs are deeply concerned about the US announcement about Jerusalem
8 December 2017
"The US announcement to recognize Jerusalem as the capital of Israel and move its embassy to the city is an ill-advised move affecting both Palestinians and Israelis", AIDA, a coalition of over 80 humanitarian, development and human-rights organizations working in the occupied Palestinian territory (oPt) stated today.
Because the President's announcement lacked balance by pointedly omitting to reciprocally recognize Jerusalem as Palestine's future capital, it is likely to have dire implications for the prospect of a peaceful and just solution to the conflict, and to increase the risk of violence for everyone living in the oPt and Israel.
AIDA said the decision will exacerbate the already flagrant pattern of violations of International Humanitarian Law and International Human Rights law, and likely increase the existing grave humanitarian and development needs of Palestinians.
The US announcement effectively recognizes Israel's unilateral annexation of East Jerusalem, which the international community and UN Security Council have consistently refused to do. According to international law, East Jerusalem is an integral part of the occupied Palestinian territory and Third States, including the US, must refrain from any actions whichmay, even implicitly, be seen to recognize Israel's unlawful annexation of East Jerusalem. Furthermore, this US announcement stands in direct opposition to international law's strict prohibition against acquiring territory by force.
AIDA urges the US Administration to abstain from taking any additional unilateral actions which may further inflame the situation, and to focus efforts on support for a lasting peace and an end to the conflict, and to Israel's 50 year-long occupation of the Palestinian territory.
(ENDS)
AIDA ウェブサイト
http://www.aidajerusalem.org/