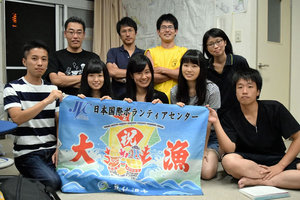みなさん、はじめましてこんにちは。今年度JVCのインターンで広報のホームページ(HP)を担当している田中春音です。現在大学4年で大学に通いつつ、東京事務所でHPの更新の仕事をしています。普段は他の方の記事を更新していますが、こうやって自分で記事を書くのは初めてなので少し緊張しています。
だいぶ更新が遅れてしまいましたが、8月にJVCの活動地の一つである気仙沼にパレスチナインターンの大室さん、同じ広報インターンの西川さん、南アフリカインターンの桒名さん と一緒に行ってきました。暑すぎず(関東と比べるととても涼しい!)気持ちのよい天気の中 、視察することができました。
震災から5年がたち、今被災地はどうなっているのか、2泊3日の短い期間の滞在でしたが、ここで現在の気仙沼について私の視点からお伝えしたいと思います。
新たに建つ住宅
まず初日は気仙沼事務所現地スタッフの岩田さん達に活動地と震災後の街を案内してもらうことに。
震災後 、気仙沼では、多くの地域でかさ上げを行っており、今回はその工事現場をよくみかけました。(かさ上げ:震災後の地盤沈下した所に土を盛ることです。鹿折地区集合型災害公営住宅付近では3.5mのかさ上げが行われました。)
かさ上げ現場を見ると、思ったよりも上がっていないように見えましたが、実は土地全体が上がっているためだそうです。
次に気仙沼市によって建てられた集合型災害公営住宅と新たに高台に移転した住宅を見学しました。
こちらの集合型災害公営住宅は入居開始が7月末に始まったためか、まだ住んでいる人は少ないようです。とてもモダンな建物ですが、周りにこういったマンションのような建物がないため、なんだかこの公営住宅だけ浮いてるように見えました。
新たに高台に移転して建てられた住宅街は、道幅が広く作られているだけでなく、道を緩くカーブにすることで、それぞれの家がみえるように工夫しているそうです。都心だと家と家の間隔とても狭く、道も狭い印象がありますが、ここ気仙沼の新しく移転した高台では住民たちも建設する際、まちづくりルールなどを話し合って決めているため、お花が道に植えてある地区など、様々な工夫を見ることができました。(住宅ついての詳しい内容はこちら)私の住宅街のイメージは狭い土地に何件も家が建っているというイメージだったので、この住宅街を訪問して、自分も住むならこういったところに住みたいなと思いました。
震災後初!地元の人々によって開催された鹿折復興盆踊り大会
二日目は鹿折復興盆踊り大会のお手伝いをさせていただきました。地元の高校生と協力しあって金魚すくい、かき氷、飲み物、わたあめを販売しました。
ちなみに初日に少し時間に余裕があったので、街を自転車でサイクリングをしたのですが、時期は夏休みにも関わらず若い人、特に子どもたちに会わない!と思っていたら、このお祭りではたくさんの子どもたちが集まっていました。
実はこの鹿折復興盆踊り大会は震災後始めて地元の人々が発起人となり、開催されました。 震災から5年たった節目のこの年、新たな公営住宅の建設や、鹿折復幸マートの別れ 、震災で亡くなられた方々への慰霊、また、新たに鹿折に戻ってくる方々の歓迎などの「まちびらき」の意味があり、様々な地元の人々の思いが込められた中、開催されたお祭りでした。たまたまのタイミングでちょうどこの時期に来ることができたのは、本当によかったと思います。
*鹿折復幸マートとは
新たな生活が始まる中で・・・
お祭りではたくさんの地元の方が来られていたので、地元の人たちと関わるチャンスと思い、7月から入居が始まったばかりの新しい集合型災害公営住宅に住み始めた方からお話しを聞くことができました。
まず新しい公営住宅に住み始めた方に住み心地はどうか質問すると、最初の一言は「寂しい」と答えられていました。以前は仮設住宅に住まわれていましたが、最初はお互い知り合いではないものの、時間がたつにつれて、お隣の人たちと会話をするようになり、頻繁に近所の人たちと会話をしていたそうです。しかし現在は公営住宅に住んでいても近所の付き合いがなく住んでいる人たちが隣人と関わろうとしないことにショックを受けていらっしゃいました。また建物そのものに対しても、この公営住宅は田舎に合わせて建てられたものではなく、都会に合わせて建てられたものだとおっしゃっていました。
せっかく新しい家に住んでいても、なぜだかのびのびと暮らせない、他にも人が住んでいるはずなのに、周りに住んでいる人と関わりがないため、活気がないと寂しそうに語られる姿を見て、住むところがあればそれでよいというわけではない、もっと重要なのは人と人のつながりなのかもしれないと思いました。
また鹿折復幸マートでお店を出していた方にもお話を聞くことができました。話しを聞くと、この鹿折復幸マートが終了するのと同時に、今まで続けてきたお店を閉じられるようです。もちろんまた新たな商店街はできますが、年齢やお金のことを考えるとまた新たにお店をだすことは難しいようです。
また今はまだ仮設に住まわれていますが、これから気仙沼市が建てた集合型災害公営住宅に移住されるようです。しかし今まで平屋で生活をしていたので、マンションのような公営住宅で生活をすることに不安な思いをつのらせていました。
今回お話を聞けたのは、二人だけでしたが、こういった二人の話の状況を聞いて、物質的な支援だけでなく 、コミュニティー作りや、どういった家に住むのか、などそこに住む人々の基盤となる生活を支えることが大切であると気づくと同時に、気仙沼事業が行っている活動である生活再建、地域づくり、仮の暮らしを支えることは今の現地でとても必要なことであると改めて思いました。
震災から5年たった現地を訪問して思うこと
1000年に一度来るといわれている大津波が襲った東日本大震災。今回被災地で新たに防潮堤が建てられている現場を見てきました。しかし新たに建てられても、この防潮堤はその大津波には対応していません。また、コンクリートの寿命もあり、50~60年しか持たないたないため、そのたびに工事が必要になり、巨額なお金がかかります。この壁を見て気仙沼事務所のスタッフである岩田さんが完璧な防潮堤なんて存在しない、と言っているのがとても印象に残りました。そして、かつてここで漁をしていた人たちがいたこと、海が見えるはずなのに、今は大きな壁で何も見えないこと、そして今回きたような津波には対応できないことを考えると、この防潮堤は本当に意味のあるものか、人々を守ってくれるものなのか、と思わずにはいられませんでした。
今回訪問して気づいたことが主に二つあります。一つが自分が想像するよりもはるかに、復興には途方もない時間がかかるということです。行く前はもう仮設の建物はほとんどなくなっているだろうと思っていましたが、現在でも、仮設住宅に住む人々、大きな商店街はなく仮設の中にそれぞれのお店を経営している状況を見て、復興するにはとても時間がかかるということを改めて知ることができました。
今まで住んでいた家、仕事、大切な地域コミュニティー、すべての環境が変わり、元の形には戻れずとも、それでも、新たな生活に向け一生懸命に生きていく姿をみて、現地の人たちの強さを肌で感じました。
もう一つが支援の難しさです。沿岸にそびえ立つ大きなコンクリートの防潮堤、新たな住宅でのコミュニティの構築など、ただ住む場所を与えればよいのではなく、そこに住む人々のコミュニティーや暮らしのあり方、そういったことも考えなくてはならないと思います。やっと新しい家に住めたとしても、また新たな環境のもと、一から新しい住民とコミュニティーを築くのには、相当な忍耐力が必要です。震災前のようには暮らせないからこそ、よりミクロな視点からの支援が必要であると感じました。
震災から5年たった現在、メディアで被災地について取り上げられることが少なくなっています。しかし地震大国である日本で、これから起こる地震に備えて、被災地から学ぶことは多くあります。この5年の間、どうやって復興活動が行われたのか、また、新たな地域のコミュニティーの作り方など、どのようにして復興していくのか、被災地だけの問題でなく、日本に住む全員が考えなくてはならないと思いました。
番外編!気仙沼のおいしいものといえば・・・
今回活動地も見学するだけでなくもちろんおいしい食べ物もたくさんたべてきました!やはり海に近いためか海鮮は絶品!!今回、気仙沼で食べた美味しいもの紹介したいと思います。
他にもあのご当地キャラクターのホヤぼーやのホヤや、気仙沼の珍味であるサメの心臓であるモウカの星なども食べて来ました。関東でも色々と海鮮も食べますが、やはり現地で獲れるものは違う!おいしい!いや、この違いを言葉で説明するのは難しいので、ぜひ気仙沼に行って食べてもらいたいです。
最後にみんなで記念撮影
この活動への寄付を受け付けています!
今、日本全国で約2,000人の方がマンスリー募金でご協力くださっています。月500円からの支援に、ぜひご参加ください。
郵便局に備え付けの振込用紙をご利用ください。
口座番号: 00190-9-27495
加入者名: JVC東京事務所
※振込用紙の通信欄に、支援したい活動名や国名をお書きください(「カンボジアの支援」など)。
※手数料のご負担をお願いしております。
JVCは認定NPO法人です。ご寄付により控除を受けられます(1万円の募金で3,200円が還付されます)。所得税控除に加え、東京・神奈川の方は住民税の控除も。詳しくはこちらをご覧ください。
遺産/遺贈寄付も受け付けています。詳しくはこちらのページをご覧ください。