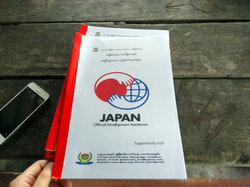更新の期間があいてしまいましたが、タイに出張に行ってきましたので、タイ南部パンガー県の情報を更新します。JVCの支援者である敷島製パン労働組合の方々と一緒に、ひさびさに活動地に行ってきました。ビルマ/ミャンマー国内の民政移管が進んでいますが、タイには今でも多くのビルマ人労働者が暮らしいています。
先日のニュースで「ロヒンジャ/ロヒンギャ」と呼ばれているムスリム系住民がビルマ/ミャンマーからボートで国外に脱出することが取り上げられましたが、ビルマ/ミャンマー国内から多くの人々が陸や海を経由して、他国に移住をしています。正式な統計はありませんが、現在も数百万人がタイへ移住していると言われています。JVCの活動地のタイ南部パンガー県も、ビルマ人労働者が約20~30万人いると言われています。私のタイ出張時に、ボートで流れ着いた女性と子供の移民約70名がタイ政府の運営するシェルターで保護されていました。現地NGOの話では、大人数がシェルターで保護されるのは2回目だということでした。漂流した方に関しての話を伺うなかで、ビルマ/ミャンマー国内にいる身内に安否を告げられていない、ブローカーに無理やり連れてこられたという方もいました。一定の手続きの後、ビルマ/ミャンマーに送還されるという事ですが、根本の問題が解決しなければ、またボートに乗ることになります。「ロヒンジャ/ロヒンギャ」を巡る問題は多いため、今後もウオッチを続けていきます。
【1】活動地を訪問した時期は5月末ということもあり、時折大雨に遭遇し、雨季にちょうど入ったところです。この時期は現地の雨季にあたり、熱帯特有の蚊を媒介するマラリアやデング熱が流行する時期でもあります。そのため、ビルマ人労働者を対象に、マラリアに対する注意喚起を促しました。蚊帳の使用を促すのはもちろんのこと、症状や治療へのアドバイスをしました。
【2】文字を読めない参加者もいるので、わかりやすく口頭で説明し、ポスターの活用もしています。(それでも、ちょっと文字が多い気がしますが。)僻地に住んでいる方が多く、近くに病院がないため、万が一のことを考えながらも、日々の病気の予防は欠かせません。
【3】資料の表紙には、日本政府の支援マークが載っています。日本政府の支援を受けたビルマ語のブックレットのようです。マラリアだけではなく、デング熱のことや、手洗いなどの衛生面の管理についても書かれています。
【4】今回の研修が行われた場所は島の僻地にあるため、ボートを使って車ごと移動しました。この島に住んで働くビルマ人労働者は緊急時にも船で本土に移動しなければなりません。
ビルマ/ミャンマーの経済発展は著しいものの、今での多くの在タイのビルマ人労働者がタイで働いていることを見てきました。いつになれば、経済発展の恩恵を受けることができるのでしょうか。引き続きビルマ人労働者の命と健康を守る活動や活動地の現状をお伝えしたいと思います。