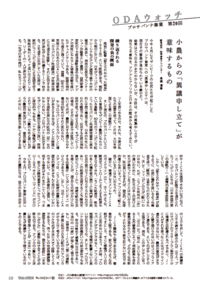今年4月にモザンビークの住民たちが起こしたプロサバンナ事業への「異議申し立て」は、現在その審査が進められている最中だ。
結果はどう出るかまだわからないが、今回は、その異議申し立てが持ちうる意味を、アジアとアフリカと日本との関係から考えてみたい
繰り返される開発の負の側面
高岩仁監督『教えられなかった戦争』(1992年)という映画がある。戦前 から戦中にかけて、日本がフィリピンやマレーシアなどアジア諸国で燐や木材の確保に奔走し、現地の住民をプランテーション労働者として雇用し、自然破壊と差別の下で経済侵略を進めながら、アジアの民衆にもたらした惨禍の実態を描いたドキュメンタリーである。映画は現代から過去に遡っていく。冒頭、80年代に実施された日本のODAによる円借款事業「カラバルソン地域開発」が地域住民に立ち退きを強要し、それに反対する住民が涙ながらに抗議するシーンで始まる。立ち退きに反対していた住民は、最終的にフィリピン国軍による発砲を伴う強制代執行によって追い出されてしまう。リーダーの一人が涙ながらに訴える。「なぜ日本は再び、私たちフィリピン人を苦しめるのか。それも、今度は私たちの国軍を使って。これは、大日本帝国による第二の侵略だ!」
そして現在の、プロサバンナというODA事業がモザンビーク農民にもたらし ている事態は、80年代のフィリピンで起こったカラバルソン地域開発事業と基本 的には同じ構造である。日本のために行われる開発であり、反対する住民は現地政府を使って押さえ込む。モザンビークの場合、さすがに武器までは使用していないようだが、農民に対する嫌がらせや脅迫は80年代のそれと変わらない。
もしプロサバンナとカラバルソンに違いがあるとするならば、こうした問題に対する現地住民たちの批判の「形」なのかもしれない。プロサバンナに反対するモザンビーク農民の主張は力強い。同時に理知的でもある。「十分に情報が公開されていない」、「小農のためと言いながら小農民の参加がないし、意見も聞いてくれない」、「農民を分断しようとする政府やJICAは信用できない」などなど。一方、カラバルソン計画で立ち退かされたフィリピン人たちは、「日本帝国の第二の侵略だ!」と感情的非難を前面に出している。
しかし、『教えられなかった戦争』が語るように、住民に犠牲を強いるような構造を持つ「開発」は昔から行われてきたし、決して、フィリピンの方が「酷い」わけはない。ただ、こうした批判の「形」の違いのために、私たち日本人の受け止め方が異なってしまうことはないだろうか。別の言い方をすれば、歴史的/地理的遠さもあいまって、アフリカを「軽く」見ているふしはないだろうか。
確かに、環境アセスメントやJICAのガイドライン(GL、注1)のような、開発をコントロールしようとする制度も整えられてきた。こうした制度は、無名の多くの犠牲者の屍の上に専門家と市民社会の協力の下に打ち立てられたものであり、この制度を活用することで開発を適切にコントロールし、持続可能な社会を築くことが、過去からの呼びかけに対する応答責任(レスポンシビリティ)のひとつであろう。しかし、当のJICAスタッフは、こうした制度の背景にある歴史的重みをきちんと受け止めていないのでないか。GLを恣意的に運用し、適用する事実がそれを示している。つまり、彼らには開発事業をしっかりコントロールすべきという「マインド」が欠けているのだ。
今年4月、プロサバンナ事業に反対してきた農民たちは、自らの生活や治安上のリスクをおして、JICAへの異議申し立て手続きに踏み込んだ(注2)。プロサバンナのマスタープラン策定は十分に環境社会配慮されるべきであり、JICAがそれを怠ったことはガイドライン違反なのではないか。農民の意見がきちんと聞き届けられないのはコンプライアンス違反である、というのが申し立ての主張である。現在、この申し立てに従って、「中立」かつ「独立」しているとされる3名の審査役によって現地調査も含め審査が進められている。どのような判断が下されるか予断を許さない状況である。
JICA職員も人間であるならば、審査役も人間である。彼らがどのような判断が下すにしろ、そこに感情が入り込むことは否めないであろう。その時、プロサバンナがアジアではなく、アフリカの問題であるという理解が影響しないと言い切れるだろうか。ましてや、プロサバンナは安倍政権肝いりの政治案件でもある。政治は極めて感情的な世界であり、今流行の「忖度」が強く働く場である。もし、外務省やJICAが「第二の侵略」と声高に批判される心配のないアフリカだからと甘く考えているのであれば、そのツケは必ず未来に大きく回帰してくるであろう。待ったなしの地球規模課題に直面する私たちは、歴史を教訓に「未来のしがらみ」に果敢に向き合うことが必要なのである。アフリカの小農たちと良い関係を築くことが「未来」であり、小農たちが異議申し立てで問うているのはそのことである。
※注(1)JICA環境社会配慮ガイドライン http://ngo-jvc.info/2i5jSEu
※注(2)JICAサイトよりhttp://ngo-jvc.info/2tlA0Sm。 50ページにわたる異議申し立ての日本語訳が掲載されている。