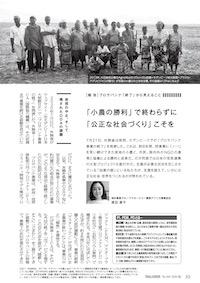「小農の勝利」で終わらずに「公正な社会づくり」こそを
7月21日、外務省は突然、モザンビークでの「プロサバンナ事業の終了」を発表した。これは、約8年間、同事業に「ノー!」を言い続けてきた現地の小農と、市民、国内外のNGOの連帯と協働による勝利と成果だ。
だが同国では日本の官民連携の大型プロジェクトも進行中だ。支援が必要な状況を生じさせている「加害の側」にいる私たちが、支援を超えて、いかに公正な社会・世界をつくれるかが問われている。
突然の中止。そして残されたODAの課題
2020年7月21日、外務省がウェブサイト(在モザンビーク日本大使館HP)で「プロサバンナ事業の終了」を発表した。外務省・JICA(国際協力機構)は、その前週まで事業を続ける姿勢を見せていただけに、まさに寝耳に水だった。
プロサバンナ事業...
正式名称は「日本・ブラジル・モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発プログラム」。日本とブラジルが連携し、モザンビーク北部3州の1110万haの土地(日本の全耕作面積の2倍)を農業開発し、事業開始当初は主に輸出用大豆の栽培を目的とした。中小農民40万人に恩恵がおよぶと謳ったが、農民の土地の収奪や環境破壊が予測された。最大の問題の一つは、当事者の農民が計画の詳細を知らされず、計画への参画もできないことだ。
事業の経緯については以下を参照。
http://mozambiquekaihatsu.net/story.html
以来、本稿を執筆中の9月下旬に至るまで、外務省・JICAからは、約35億円もの税金が投じられた事業が、どのような理由と経緯で終了したのかの説明はない。
プロサバンナ事業は、研究・技術移転能力向上プロジェクト(PI)、コミュニティ開発モデル策定プロジェクト(PEM)、マスタープラン策定支援プロジェクト(PD)の三本柱など(下記のコラム参照)で構成される。本来13年に完成しているはずが、約8年間にわたる現地小農らの抵抗運動により、事業の根幹「マスタープラン」が完成しないまま事業が終わったことは、事業の「中止」「頓挫」を意味する。
PI、PEM、PDとは...
P I : 「適正な作物・品種、栽培技術の開発とともに、研究開発体制の整備」を目的とし、主に日本など国際市場へ輸出目的の大豆生産技術に焦点をあてている。
PEM : 「すぐ成果の出る小規模プロジェクト」として小農組織支援や契約栽培支援などを実施し、これをモデル化しようとするもの。契約栽培支援では、融資した地元のアグリビジネス企業による小農の土地収奪が判明。JICA・外務省に対応を求めたが何らなされなかった。農業資材をばらまき、事業への「賛成派農民」づくりに使われてきた。
PD: 数十年にわたる農業開発の青写真を描くもの。この策定プロセスへの小農や市民の「参加」をめぐり、さまざまな問題、脅迫・介入・分断・排除などの人権侵害が起きてきた。
だが外務省・JICAは、それでも今回の終了を「完了」だと主張する。この自らの非を認めず、隠蔽し、そこに「ごまかし」を上塗りしてきた姿勢こそが、プロサバンナの特徴で、事業下の状況を悪化させてきた最大の要因と言える。
プロサバンナ事業は、外務省・JICAが、小農や市民・NGOが調査などで確認し、指摘してきた人権侵害、問題の全てに何ら対応することなく、終わった。現地の司法判決(注1)にも応えていない。JICAに至っては、現地市民社会への介入・分断・排除という人権侵害を、自ら引き起こしてきた。
今後のODAにおいて、現地から再び反対の声があがったときに、果たして日本がどう対応できるのか。プロサバンナが中止に追い込まれたとはいえ、残念ながら、その道筋と可能性はいまだ見えないままだ。
◎注1...司法判決。2017年、モザンビーク弁護士会が「プロサバンナ調整室を所管する農業省」を「人びとの知る権利を侵害」していると提訴。2018年8月に全裁判官一致でこれを認容。判決から10日以内に「プロサバンナ事業によって影響を受けるコミュニティの土地・食料安全保障・栄養に関連する情報」の全面開示が求められたが、モザンビーク政府もJICAも一切対応していない。なお「プロサバンナ調整室」はJICAが資金を出して創設、雇用スタッフを派遣し、運営費を拠出してきた。
小農・市民の連帯がもたらした「勝利」
事業の中止後、メディアなどの取材で必ず受けた質問が「これで現地の土地収奪や被害をもたらす開発などは止みますか」というものだ。残念ながら答えは「ノー」だ。現地では問題が山積している(下記コラム参照)。そして前述のとおり、ODAにおいても多くの課題が残る。
そうだとすると、プロサバンナが終わりを迎えたことは意味がなかったのか。この答えも「ノー」だ。社会運動の観点から見れば、その意味・意義はとても大きい。
「海外投資促進による大規模農業開発事業・プロサバンナ」が構想された背景として、当時のJICAの資料には、モザンビーク北部に暮らす小農の農業は「伝統的な農法で、低い生産性が問題」だとして描かれ、ゆえに「土地が有効活用されていない」とされていた。
これが批判の声を受け、その後のマスタープラン・ドラフト改訂版(対話に基づいて策定するとされながら、知らないうちに作られていた)においては、大規模農業開発の構想が消え、食料生産と環境保全に貢献するとして家族農業の重要性が語られるようになった。しかし、それでも国際市場に接合した農業こそが持続可能であるとし、小農の「農業形態とマインドセット」を「変える必要があるもの」として描く点は、最後まで変わらなかった。
すなわち、小農はあくまでも「変えられる対象」=「客体」であり続け、「発展の主体」とはみなされなかった。つまり外務省・JICAは、8年間を通じて、小農(そして私たち日本の市民社会)を軽視してきたのだ。それは、本人たちがいくら隠そうとしても「やられた側」にはすぐにわかる。
だからこそ、小農たちは何度も来日し、事業がいかに利益をもたらすかの説明を繰り返す外務省・JICAに対し、「私たちがほしいのは利益ではなく、権利、主権そして尊厳だ」と訴えてきた。小農にとってプロサバンナ事業の受け入れは、自分たちとその農業が「価値が低い」と評価されることでの開発、そしてそれを可能とする社会・世界のあり方を許すことを意味した。
「反対の声を翻すよう」現地政府に脅され、恐怖を覚えながらも、8年間にわたり事業に「ノー!」をつきつけ、事業内容よりも実施(事業策定)プロセスにこだわり続けたのは、自分たちが「取り込まれる」のではなく「主体的」参加を求めたからだ。
プロサバンナへの抵抗は、「真の参加・対話」の実現を通じて、小農とその農業が尊重され、自分たちが発展の主体となる社会・世界を目指すという社会変革運動でもあった。
それを象徴するのが小農リーダーのエレナさんの言葉だ――「私は私のために闘っているのではありません。私たちの子どもたち、すなわち次の世代のために闘っています。そして、私の国のすべての小農たちのために闘っています」
この意味において、今回、小農たちから「ノー!」を突き付けられ続けたマスタープランが完成されず、事業が「中止に追い込まれた」ことは、単に「問題の多い事業が終わってよかった」にとどまらない。プロサバンナ実施主体の3カ国の小農や市民・NGO、一連の活動の支援者、メディア、国会議員など多くの関係者が連帯・協働しての事業中止の実現は、「人びと」の側の重要な勝利と成果だった。
市場原理のみを価値の尺度とし、弱肉強食的な発想のもとで「弱者」を排除する新自由主義的な考え方や仕組みに支配された世界に対抗するための大きな一歩だった。世界は問題だらけだが、この一歩がなければ次の一歩もない。
プロサバンナ事業は終わったが......
モザンビーク北部では、同事業もその一環だった、資源・インフラ・農業開発が一帯となる「ナカラ回廊開発」が、引き続き日本の官民連携で進行中。天然ガス開発地では、環境・生業破壊、強制移転、格差拡大といった社会問題が生じ、「収奪型開発の象徴」への不満を背景に、数年前からISを名乗るイスラム系武装グループが台頭し、武力攻撃・衝突が生じ、国内避難民が30万人を超える紛争状態となった。この開発に、JBIC(国際協力銀行)等を通じて日本の莫大な公的資金が投じられている。JVCはこの問題に取り組み始めている。
声明は以下。
https://www.ngo-jvc.com/jp/projects/advocacy-statement/2020/07/20200729-mozambiquestatement.html
発展の主体としての小農と世界への貢献
本当に、ODAを受ける現地の人びとは発展の主体になりえないのだろうか。プロサバンナ事業に対し声をあげてきたモザンビーク最大の小農組織UNAC(全国農民連合)の声明は、小農を「地球の守護者」と呼び、その農業が「地域経済の主柱で、尊厳ある雇用創出が可能で、国民のために質量十分な食料を生産し、食料主権の達成に貢献する」と認識し、「国内消費のための小農による食料生産を通じた内発的な潜在性を発展させるべき」とのビジョンを描いている。
実際、モザンビークに限らず世界の小農は、自然環境を守り、その恵みを活かした農業で世界の食料の8割を生み出し(注2)、土地に根ざした多様でおいしい作物、それに基づく文化・風土を作りだしている。
一方、新自由主義経済のもとで「強者」=「マネー」に都合いい仕組みや政策が蔓延するなか、小農は苦しい状況に置かれている。それでも、UNACも一員である世界的小農運動ビア・カンペシーナ(注3)などは、世界の人びとと連帯し、自らの実践、権力・抑圧への抵抗運動を通じて得た経験や知見を、「食料主権」「アグロエコロジー」などの新しい価値や運動に転換して世界に提示し、18年12月、国連総会で承認された「国連・小農権利宣言」(注4)という世界的な規範に昇華させてきた
こうしてみると、モザンビーク(や世界)の小農の闘いは遠いアフリカで起きていることだが、一人ひとりの権利や主権と尊厳を守り、誰にも居心地のいい社会のあり方を求め、地球環境を守るという点で、日本の私たちの暮らしにもつながっている。様々な意味で世界に貢献している。
モザンビーク、あるいは国際社会に対し、日本に暮らす私たちが「支援を行う側」として接する状況は互いの関係性の「ほんの一面」にすぎない。私たちは支援が必要な状況を生じさせる「加害の側」にいる可能性が高いし、一方で、目に見えないところで、他国に暮らす人びとの奮闘による恩恵を受けている。
自分自身がいま享受している自由や権利、その上にある暮らしは、モザンビークの小農のように、被抑圧・弱者の立場に置かれながら、命がけで「ノー」と言い続けた/る人びとがいることでもたらされたと痛感する。そのおかげで、世界は、かろうじて「マシな」状態に保たれているのだとすら思う。
一方、この意味において、私たち日本の市民は、国際社会に対して「支援/資金を提供する」以外に、「よりよき世界」のための貢献ができているだろうか。
◎注2...小農の食料生産については以下のサイトを参照。https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kanren_sesaku/FAO/undecade_family_farming.html
◎注3...ビア・カンペシーナ(La Via Campesina)。スペイン語で「農民の道」を意味する小農組織。1993年に発足、2020年現在、81カ国から約2億の小農が加盟。新自由主義的なグローバル化に対してNGOなどと協力しながら、抵抗運動、提言を行ってきた。
◎注4...国連小農権利宣言。正式名称は「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」。小農はその土地の食料や土地、水などの自然資源に権利を有し、その文化的アイデンティティや伝統知識の尊重、種子や生物多様性に関わる権利が保護されるべきとうたった。小農の世界への貢献を認めた点でも画期的な宣言と言われている。
「支援をする私たち」を超えて
プロサバンナの抵抗運動(12年10月~20年7月)を通じて私が体感し、愕然としてきたのは、外務省・JICAの劣化に加え、自戒を込めて言うと、(一概には言えないが)日本の市民社会と民主主義の衰退だった。
それは、一人ひとりの尊厳や人権が軽んじられ、公正な社会の担い手としての私たち市民一人ひとりの役割とそれを実現するための主権が自分の手にあることを忘れているということだ。そのために、「表層的な現象(問題)」への対処療法にとらわれ、政治や権力に向き合う際には「公正」であろうとする前に、「中立」「友好的」であることがよしとされ、他方で、「事実に基づいた建設的批判」は「非難」や「誹謗中傷」と混同される。だが、それで誰に何をもたらせるのだろうか。
こうした社会のありようが、税金を使って行われる援助(ODA)のありようにも表れるのだと感じる。
私は、13年に本誌連載「ODAウォッチ」で最初に執筆した原稿で、当時来日したUNAC事務局のヴィセンテさんが、外務省・JICAに対しプロサバンナについて問題提起したときの言葉を引用した。
「これは人としてのモラル、人間性そして連帯の問題なのだ」
プロサバンナへの抵抗運動が始まったばかりの時点で、こう喝破した、当時まだ20代だった彼は、あらためてすごかったと思う。
対プロサバンナの活動を通じて出会ったモザンビークと世界の小農や人びとは、それまでぼんやりしていた私に、強烈な主権者意識とその可能性を見せてくれた。それは、他者への共感と広い視野をもたらし、遠く離れた人びととビジョンを共有、連帯し、多様な可能性を見出しながらの「よりよき世界」を実現する社会変革が可能だと教えてくれた。
無論、現実には「100闘って負けて1得られるかどうか」だが、99の負けはゼロではなく、様々な可能性を秘めている。私たちは微力だが無力ではない
一方で、「支援をする私たち」にとどまっている限り、こうした可能性は見えないし、希望も見えてこないだろう。だからこそ、今、自分が暮らす日本の社会のありようはこれでいいのかとの自問自答が続く。
事業地ナンプーラ州農民組織の代表で、過去4回来日したことのある小農、コスタさんが、かつて日本の市民に訴えていたことを、ここであらためて記したい。
「今モザンビークで起きていることは『悲しみの開発』です。あるいはそれは、『犠牲を伴う開発』ともいえるでしょう。私たちにそんな開発は必要ありません。私たちが欲するのは『幸福のための発展』です。あなたがたはそのために何ができますか?」
プロサバンナ事業は終わったが、この状況を前にして、私たちは今、コスタさんの問いにどのように答え、応えられるだろうか。