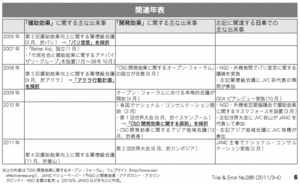「CSO開発効果」が生まれた経緯
CSO ( 市民社会組織 ) という呼び名からしてなじみが薄いかもしれない。その定義は別欄にゆずるとして、ここでは NGOを含むそのCSOが実施する開発の効果を問う議論がどのように生まれてきたかの経緯を振り返る。次ページに掲載した年表と合わせてお読みいただきたい。(編集部)
NGOが援助効果のプロセスに参加
援助改革を目指して〇五年に採択されたパリ宣言。〇七年、OECD/DAC(以下DAC)はこのパリ宣言の各国における実施状況を発表した。この内容にアメリカ政府が批判し、それにNGOが反論したことをきっかけに、パリ宣言を実現するためのプロセスにNGOが参加することになった。このプロセスはDAC内の援助効果作業部会が担当しており、NGOはこれを外部から監視する立場であったが、NGOの意見をより反映させるために「市民社会と援助効果に関するアドバイザリーグループ」が設置されたのである。
また、〇八年にガーナの首都アクラで開催された「第三回援助効果向上に関する閣僚級会議」(以下アクラ閣僚級会議)以降は、この援助効果作業部会自体にもNGOから二名の代表が参加するようになった。
こうして、援助改革の議論にNGOは政府と対等な立場で参加するようになっていった。
「CSOも開発の主体に」アクラ行動計画が後押し
そもそも「CSO」という言葉が日本ではなじみが薄い。パリ宣言プロセスに関わるNGOが自らを「CSO」と表現するのは、政府や民間企業に対して市民を代表しているという立場を明確にするためである。また、「開発効果」という言葉には、「援助効果」の議論が技術論に陥りがちな現状への批判を込めて、援助は開発に資するべきとの主張が含まれている。
パリ宣言のプロセスにNGOが正式に参加すると同時にNGO自体が自らの開発効果を高めるための議論を加速させたのは、アクラ閣僚級会議で「アクラ行動計画」( AAA : Accra Agenda for Action) が採択されたことが大きい。このAAAでは、民主的なオーナーシップの主体として援助受入国政府のみならずCSOもその対象とされた(第十三項)。同時に、CSOが独自の開発アクターであり、援助の議論への参加が促されたこと、その活動環境を整えることも示された(第二十項a、c)のである。
「CSO開発効果に関する原則」を採択
アクラ閣僚級会議後、CSOはCSO開発効果を世界中のCSOが参加して議論する仕組みとして「CSO開発効果に関するオープン・フォーラム」を設立した。このオープン・フォーラムでは、世界のいかなるCSOも参加できる透明で開かれたプロセスを作るために、ナショナル・コンサルテーション(国別協議)、地域別コンサルテーション、世界大会といったCSO間の協議の場を設定・開催している。一〇年九月にはイスタンブールで第一回世界大会を開催され、それまで一年以上にわたる各国・各地域での議論を集約して「CSO開発効果に関する原則(イスタンブール原則)」が採択された。
そして現在は、この原則を実際のCSOの活動に適応するためのガイドラインと指標、および政策環境(CSOがその原則に基づいて役割を発揮できる政治・社会的な条件)を取りまとめるプロセスにある。今年六月にはカンボジアで第二回世界大会が開催される予定であり、ここでCSO開発効果に関する基本的な枠組みを決め、同じく十一月に韓国釜山で予定されている第四回閣僚級会議において各国政府にその枠組みを認知・賛同するよう働きかけることになる。
日本のNGOも参加を
日本のNGOは、遅ればせながらこのオープン・フォーラムのプロセスに参加した。上記イスタンブール会議に国際協力NGOセンター(以下JANIC)を代表して谷山が参加したのが最初である。また今年二月、イスタンブール会議の時点ですでに六十五ヵ国で行なわれていたナショナル・コンサルテーションを、JANICが主催して日本でも開催した。
このCSO開発効果の議論は、国際的な広がりをもっており、これまでに世界各国で二千以上のCSOやNGOが議論に参加していると言われている。CSO/NGOが実施する開発が虐げられている人々の状況の改善のために真に資することができるかを問う議論として、CSO開発効果の議論は画期的なものと言える。また、いまだ日本のODAは巨額でありその影響力も大きく、日本のNGOにはそれへの働きかけが期待されている。日本のNGOのネットワークであるJANICとしても、またJANICに副理事長を出しているJVCとしても、この国際的な議論に参加し、自らの活動の振り返りに役立てる必要がある。
(※記事内の一部参照先は冊子掲載時と異なっています)